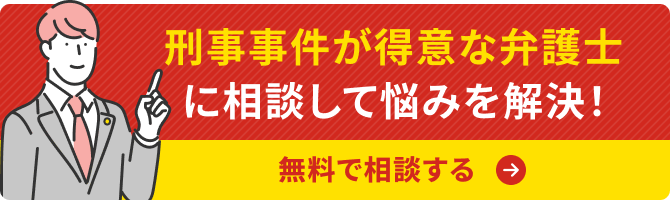- 「大切な家族が懲役刑を受け、刑務所に収容されることになった」
- 「しばらく会えないかもしれない」
このような現実を前にして不安や寂しさを感じている一方で、「仮釈放」という制度の存在を知り、少しでも早く再会できる可能性に希望を抱いている方もいるのではないでしょうか。
仮釈放は、一定の条件を満たせば刑期の途中で出所できる制度ですが、その仕組みや条件はやや複雑です。
十分な理解がないままでは、誤解や不安が募ってしまうこともあるでしょう。
そこで本記事では、仮釈放の仕組みや仮釈放が認められる条件、仮釈放が決まるまでの流れ、仮釈放後の生活における制約や注意点について解説します。
家族としてできることを整理し、少しでも安心して前を向いて過ごせるようになるためにも、ぜひ参考にしてください。
仮釈放とは? | 制度をわかりやすく解説
まず、仮釈放の仕組みについてわかりやすく解説します。
仮釈放とは刑期満了前に身柄が解放される制度のこと
仮釈放とは、刑務所に収容されている受刑者が、一定の条件を満たした場合に、刑期を全て終える前に一時的に社会復帰を許可される制度です。
仮釈放の目的は、受刑者が社会の一員として再出発できるよう、更生を促し、円滑な社会復帰を支援することにあります。
仮釈放中に問題を起こさなければ残りの刑期が免除される
仮釈放期間は、残りの刑期にあたる期間とされます。
たとえば「懲役5年」の判決で2年服役したあとに仮釈放された場合、仮釈放期間は「3年」です。
仮釈放中は、保護観察のもとで生活しなければなりません。
保護観察とは、刑務所の外で社会生活を送りながら、更生に向けた支援や指導を受ける制度です。
釈放中に再び罪を犯すなどの問題がなければ、残りの刑期の服役は免除され、仮釈放期間終了時点で刑期を終えたとみなされます。
なお、無期懲役の場合は明確な刑期がないため、仮釈放後も死亡するまで仮釈放の状態が続きます。
ただし、仮釈放が取り消されない限り、社会での生活を続けることが可能です。
仮釈放はどれくらいの割合で認められる?仮釈放が認められるまでの平均期間は?
ここでは、仮釈放が認められる割合や、認められるまでの平均的な期間について、法務省の統計や制度の仕組みをもとにわかりやすく解説します。
仮釈放者は全出所受刑者のうち約6割
法務省が公表した「令和6年版 犯罪白書」によると、令和5年に仮釈放された受刑者は10,211人でした。
一方で、刑期を満了して釈放された受刑者は5,991人だったこともわかっています。
つまり、受刑者の約63%が仮釈放により出所しており、満期釈放よりも仮釈放のほうが多いということです。
仮釈放が認められることが最も多いのは刑期が80%~90%経過してから
法務省の「令和6年版 犯罪白書」によると、令和5年に仮釈放が認められた受刑者の刑の執行率は、以下のとおりでした。
- 90%以上:34.3%
- 80%以上90%未満:47.2%
- 70%以上80%未満:17.3%
- 70%未満:1.2%
このように、仮釈放が認められるのは、基本的に「刑期の70%以上」を経過したタイミングがほとんどであることがわかります。
仮釈放と釈放・保釈・執行猶予の違い
釈放に関連する用語としては「仮釈放」のほかにも、「釈放」「保釈」「執行猶予」といった言葉を耳にすることがあります。
これらは、いずれも「拘束から解放される」という点では共通していますが、意味やタイミング、適用される条件は異なる点に注意しましょう。
以下、それぞれの違いを簡単にまとめました。
| 制度名 | 対象者 | 条件・特徴 |
| 仮釈放 | 有罪判決を受けて服役中の受刑者 | 一定の条件を満たした場合、保護観察付きで仮に釈放される |
| 釈放 | ・逮捕または勾留された被疑者 ・刑期を満了した被告人 |
無条件で釈放される |
| 保釈 | 起訴された被告人 | 保釈金の納付などを条件に、判決が出るまでの間一時的に釈放される |
| 執行猶予 | 有罪判決を受けたが刑務所に収容されていない人 | 一定期間新たな犯罪がなければ、刑の執行が免除される (保護観察がつく場合あり) |
ここから、仮釈放とほかの制度の違いについてそれぞれ解説します。
仮釈放と釈放の違い
釈放とは、留置場や刑務所から出所して、身柄拘束から解放されることを総称した用語です。
釈放は、大きく分けて以下の2つの意味で使われます。
| 制度名 | 対象者 |
| 起訴前の釈放 | 警察や検察に逮捕・勾留された被疑者が、起訴される前に釈放される場合で、以下のようなケースが該当します。 ・取調べの結果、微罪処分と判断された ・検察に送致されたものの、勾留請求がされなかった ・検察官が勾留請求をしたが、裁判官が勾留決定処分を行わなかった。 ・検察官が不起訴処分を行った。 |
| 満期釈放 | 実刑判決を受けた受刑者が、刑期を全て終えて出所する場合で、たとえば懲役3年の判決を受けた人が、3年間服役したのちに出所するケースが該当します。 |
一方、仮釈放は一定の条件を満たした受刑者が刑期の途中で一時的に釈放される制度であり、釈放後も保護観察付きの生活を送る必要があります。
つまり、仮釈放と釈放は、主に釈放されるタイミングと釈放後の保護観察の有無などが異なるのです。
仮釈放と保釈の違い
保釈とは、一定額の保証金(保釈金)を納めることを条件として、一時的に身体拘束から解放される制度です。
保釈は、以下のような条件を満たすときに、保釈金を支払うことで認められる場合があります。
- 刑事事件で起訴されたあと、罪証隠滅や逃亡のおそれがないと判断された場合に、第一審の判決が言い渡された時点で実刑判決を受けるまで(執行猶予付き判決、罰金の場合には釈放されます)刑事裁判が終了するまで
このように、有罪判決の場合、第一審で実刑判決を受けるまで、保釈が認められます。
一方、仮釈放は、すでに有罪判決を受けている受刑者が対象です。
つまり、保釈と仮釈放は、主に釈放されるタイミングや釈放が認められる条件などが異なるのです。
仮釈放と執行猶予の違い
執行猶予とは、有罪判決が言い渡された際に、一定の期間刑の執行を猶予する制度です。
執行猶予期間中に新たな犯罪を犯さなければ、刑の執行自体が取り消され、刑を受ける必要がなくなります。
たとえば、懲役1年・執行猶予3年という判決を受けた場合、被告人は刑務所に入る必要がなく、自宅で通常通りの生活を続け、3年間は刑の執行が猶予されます。
また、執行猶予には「保護観察付き」と「保護観察なし」の2種類があります。
一方、仮釈放はすでに有罪判決を受けている受刑者が対象です。また、釈放後も保護観察が義務づけられ、行動には一定の制限が課されます。
つまり、仮釈放と執行猶予は、対象者の刑務所への収容の有無などが異なるのです。
仮釈放が認められる条件
仮釈放は全ての受刑者に認められるわけではありません。
仮釈放が認められるかどうかは、主に以下の6つの条件を総合的に考慮して判断されます。
- 一定期間の服役を終えていること
- 十分に反省し、更生の意欲があること
- 再犯のおそれがないこと
- 更生のために保護観察が適していること
- 社会感情が仮釈放を是認していること
- 身元引受人がいること
ここでは、それぞれの条件について解説します。
一定期間の服役を終えていること
仮釈放が認められるためには、次の期間以上の服役が終了している必要があります。
- 有期懲役刑の場合:判決で言い渡された刑期の3分の1
- 無期懲役刑の場合:少なくとも10年以上
ただし、上記はあくまでも仮釈放が可能になるための最低限の基準であり、実務上はこのタイミングで仮釈放が認められることはほとんどありません。
実際は刑期の8割~9割程度を終えた段階で仮釈放が許可されるケースが最も多くなっています。
十分に反省し、更生の意欲があること
受刑者本人が自身の犯した罪に対してしっかりと向き合い、深く反省していることも大きな要素のひとつです。
「反省している」とは、単に口頭で謝罪するだけでなく、自分がおこなった行為が社会にどのような影響を与えたかなどを自覚し、悔い改める姿勢が見られることが必要です。
本人が罪を認めていない場合、たとえば刑事裁判で無罪を主張していたり、再審請求をおこなっていたりすると、反省の気持ちがあると認められにくくなる傾向があります。
また、本人に更生の意欲があるかどうかも重要です。
更生の意欲があるかどうかは、以下のような要素を踏まえ客観的に判断されます。
- 刑務所での作業や指導への取り組み状況
- 規律違反の有無
- 日常生活での態度
- 出所後の生活設計が具体的に立てられているか
再犯のおそれがないこと
仮釈放が許可されるためには、再び犯罪を犯すおそれがないと判断される必要があります。
なぜなら、仮釈放が「更生した人に与えられる社会復帰のチャンス」として位置づけられているためです。
再犯のおそれは、以下のような要素をもとに客観的に判断されます。
- 本人の性格や年齢
- 犯罪の動機や内容、悪質性
- 社会に与えた影響の大きさ
- 釈放後の生活環境(家族や仕事の有無など)
更生のために保護観察が適していること
仮釈放の判断においては、保護観察のもとで更生が期待できるかどうかも、重要な要素のひとつとされています。
更生が見込まれるかどうかは、服役中の反省の態度が認められるか、本人に更生への強い意欲があるかどうか、再犯のおそれが低いといえるか、といった要素が考慮されます。
これらの要素が揃っていると、保護観察のもとで社会生活を送りながら、更生を目指すことが現実的に可能であると評価され、仮釈放が認められる可能性が高くなります。
社会感情が仮釈放を是認していること
社会全体が仮釈放を是認しているかも重要な要素となります。
たとえば、殺人事件などの重大犯罪の被害者や家族が強い処罰感情を抱いているようなケースでは、「仮釈放を認めるのは社会的に不適切」と判断され、仮釈放が見送られる可能性が高いです。
身元引受人がいること
仮釈放制度が単なる釈放ではなく「更生のための社会復帰支援」であるという点からも、身元引受人の存在も重要視されます。
身元引受人とは、仮釈放された人の生活を見守り、社会復帰を支援する責任ある立場の人です。
単に住居を提供するだけでなく、日常生活における精神的な支えとなり、再犯防止に協力する役割が求められます。
なお、身元引受人には以下のような人が選ばれることが多いです。
- 両親
- 配偶者
- 兄弟姉妹
- その他の親族
- 知人・友人
- 雇用主
- 更生保護施設
仮釈放されるまでの流れ
仮釈放の申請は刑務所長がおこないます。
その後、仮釈放が認められるまでには、以下の流れで手続きが進みます。
- 事前審査
- 面接・仮釈放決定
- 身元引受人への通知
- 仮釈放前の準備
- 仮釈放
ここから、各手続きをそれぞれ解説します。
1.事前審査
まず、保護観察所が仮釈放審理のための事前調査をおこないます。
事前調査では、主に以下のような事項が調査されます。
- 帰住予定地(本人が出所後に住む場所)の状況
- 身元引受人の有無や支援体制
- 被害者やその関係者の処罰感情
- 受刑者の更生意欲や再犯の可能性
- 社会復帰に向けた支援の有無(就労・生活面など)
仮釈放の審査は、法務省所管の地方更生保護委員会が担います。
2.面接・仮釈放決定
事前調査を経て仮釈放審理に進むと、受刑者は2回の面接を受けます。
それぞれの面接の内容は、以下のとおりです。
| 面接 | 内容 |
| 予備面接(準面) | まずは、保護観察官が受刑者と面接をおこないます。 ここでは、本人の反省の度合いや更生の意欲、仮釈放を希望する意思の有無などが確認されます。 仮釈放を前提とした心構えや生活設計などが問われることもあります。 |
| 本面接(本面) | 次に、地方更生保護委員会の職員が受刑者と直接面接をおこない、仮釈放の妥当性について審査します。 予備面接の結果や服役中の態度(懲罰の有無、作業態度など)も考慮されます。 |
2つの面接を経たあと、地方更生保護委員会が最終的に仮釈放の可否を決定します。
3.身元引受人への通知
仮釈放が許可されると、本面接から約1ヵ月後、地方更生保護委員会から「仮釈放決定の通知」が身元引受人のもとに届きます。
通知には、以下のような内容が記載されています。
- 仮釈放の許可
- 出所予定日
- 当日の迎えが可能かどうかの確認
身元引受人は、通知に同封された返信用書類に必要事項を記入して返送します。
なお、仮釈放後に受刑者はすぐに保護観察所へ出向く必要があるため、当日は出迎えがあるほうが望ましいですが、出迎えがなくても仮釈放は実施されます。
4.仮釈放前の準備
仮釈放が決定すると、出所の約2週間前から仮釈放準備寮などに移り、社会復帰に向けた準備期間に入ります。
準備期間中は、以下のように矯正施設の中でも比較的自由度の高い開放処遇が適用されます。
- トイレが個別に設置された居室に移る
- 刑務作業が軽減される
- 洗濯機の利用やテレビの視聴が可能になる
- 再犯防止のための仮釈放前教育が実施される
5.仮釈放
出所日には、刑務作業で得た報奨金の清算や荷物の整理がおこなわれ、出所式が実施されたあと、正式に仮釈放となります。
仮釈放後は、直ちに保護観察所に出向き、保護司や保護観察官の指導・監督を受けなければなりません。仮釈放中は「刑の執行中」とみなされており、一定の遵守事項が課されます。
遵守事項を遵守しながら、社会生活の中で更生を目指すのです。
仮釈放後の生活はどうなる?普通の生活が過ごせる?
仮釈放になったとしても、刑の執行はまだ続いており、「保護観察付きの釈放」という形式で社会の中で生活しながら更生していく期間となります。
ここでは、仮釈放後の生活がどういったものになるのか、どのようなルールを守る必要があるのかについて解説します。
一定のルールを守りさえすれば、普通の生活ができる
仮釈放中でも、基本的には定められたルールを守っていれば、通常通りの生活を送れます。
たとえば、仕事を始めたり結婚したりすることも可能です。
ただし、保護観察中は「生活状況の報告義務」があるため、就職や結婚などの変化があった場合は、保護観察官や保護司に必ず報告しなければなりません。
また、旅行にも行けます。
ただし、7日以上の旅行を予定している場合には、事前に保護観察所の長の許可を受けなければなりません。
なお、遵守事項を守らなかった場合は、仮釈放が取り消されて再び刑務所に収容される可能性があるため、十分な注意が必要です。
保護観察官や保護司と定期的に面談をする必要がある
保護観察期間中は、仮釈放者は定期的に保護観察官や保護司と面談をおこない、その都度生活状況の確認や今後の指導を受けなければなりません。
面談では、仕事や家庭での困りごとなどについて相談できます。
ただし、正当な理由がないまま面談を欠席した場合には、「保護観察に従っていない」と判断され、仮釈放が取り消される可能性があるので、面談にはきちんと出席しましょう。
遵守事項を守らなければならない
仮釈放中には、遵守事項を守らなければなりません。
遵守事項は、全ての保護観察対象者に共通して求められる「一般遵守事項」と、個々の事情に応じて定められる「特別遵守事項」の2種類があります。
それぞれの遵守事項の主な内容は、以下のとおりです。
| 一般遵守事項 | 特別遵守事項 |
| ① 健全な生活を維持すること ② 指導監督を誠実に受けること ③ 住居を届け出ること ④ 届け出た住居に住むこと ⑤ 転居・長期旅行の許可を得ること |
① 特定の行動の禁止 ② 必要な行動の実施 ③ 特定の事項の事前申告 ④ 改善プログラムの受講 ⑤ 指定施設での宿泊 ⑥ 社会貢献活動の実施 |
再犯・遵守事項違反で仮釈放が取り消しになることもある
刑法第29条によると、以下の事由が発生した場合は仮釈放が取り消される可能性があります。
- 仮釈放中に新たな罪を犯し、罰金以上の刑が科されたとき
- 仮釈放前に犯した別の罪について、罰金以上の刑が科されたとき
- 仮釈放前に犯した別の罪で罰金以上の刑を受けている人に対して、その刑の執行が必要と判断されたとき
- 仮釈放中に遵守事項を守らなかったとき
なお、仮釈放の許可が取り消された場合、仮釈放されていた期間は刑期に含まれません。
仮釈放に関してよくある質問
ここでは、仮釈放に関するよくある質問をまとめました。
似たような疑問をお持ちの方は、ぜひここで疑問を解消してください。
無期懲役の受刑者でも仮釈放が認められる?
無期懲役の受刑者であっても、仮釈放が認められる可能性はあります。
ただし、認められるケースは非常に限られているのが実情です。
無期懲役の場合、10年間服役をすれば仮釈放の審査対象となります。しかし、実際の運用では、服役から約30年が経過して初めて仮釈放の審査がおこなわれるのが一般的です。
法務省が公表したデータによると、平成26年~令和5年の過去10年間で仮釈放が許可された無期懲役受刑者の平均服役年数は35.0年にのぼりました。
また、仮釈放の審査がおこなわれても、審査が認められるケースは低いです。
実際、令和5年には64人の無期懲役受刑者に対して仮釈放の審査がおこなわれましたが、許可されたのはわずか7.8%にあたる5人にとどまっています。
【参照】無期刑の執行状況及び無期刑受刑者に係る仮釈放の運用状況について(令和6年12月)|法務省
仮釈放の予定があることや仮釈放日を受刑者本人が知るのはいつ?
仮釈放の決定後、受刑者本人が仮釈放の予定や具体的な日付を知るのは、仮釈放の約2週間前です。
このタイミングで、本人は「仮釈放準備寮」と呼ばれる施設に移され、社会復帰に向けた準備が始まります。
一方、家族などの身元引受人には、仮釈放が許可された旨が仮釈放日の1ヵ月~3ヵ月前に通知されます。しかし、通知には「本人に仮釈放日を伝えないように」との警告書が同封されています。
このような取り扱いになっているのは、受刑者が仮釈放日を知ってしまうことで気が緩み、規律を乱したり、仮釈放が撤回されるような問題行動を起こすリスクがあるからです。
また、仮釈放の情報が外部に漏れることで、被害者や関係者からの嫌がらせやトラブルに発展する可能性も考慮されています。
さいごに|仮釈放に関する疑問や悩みは弁護士に相談を!
本記事では、仮釈放の制度や条件、注意点について解説しました。
仮釈放が認められると、刑務所から早期に出所できます。しかし、仮釈放が認められるには、一定期間の服役や身元引受人の存在など、さまざまな条件を満たなければなりません。
また、仮釈放後も遵守事項を守らなければならず、違反すれば仮釈放が取り消されるリスクもあります。
仮釈放の許可の可能性を高めるためには、弁護士へ相談するのがおすすめです。
弁護士に相談することで、手続きの流れや必要となる対応に関するアドバイスを受けられるだけでなく、早期釈放にむけた弁護活動をおこなってくれます。
「ベンナビ刑事事件」を利用すれば、刑事事件を得意とする弁護士を地域や相談内容に応じて簡単に探せます。仮釈放に向けて準備を進めるためにも、ぜひお早めにご活用ください。