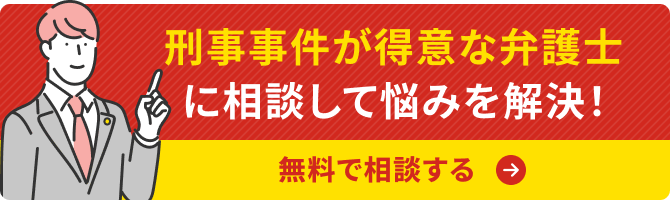- 「上司のIDを使って会社のシステムにアクセスしてしまった」
- 「悪気はなかったし、ちょっと確認するだけのつもりだった」
そんな軽い気持ちで取った行動に対して、あとになって「これは問題だったのではないか」と不安を感じている方もいるかもしれません。
不正アクセス禁止法では、他人のIDやパスワードを無断で使用してログインするといった行為を処罰の対象としており、違反が認定されれば、逮捕に至るケースもあります。
逮捕を避けるためには、正しい知識を持ったうえで早めに弁護士に相談するなどの対策が必要です。
そこで本記事では、不正アクセス禁止法の基本的な内容をはじめ、違反となる行為や法的な罰則、実際に逮捕された事例、逮捕後に進む手続きの流れについて解説します。
「自分も逮捕されるかもしれない」と不安に感じている方が今後どのように対応すべきかを判断できるようになるためにも、ぜひ参考にしてください。
他人のIDを勝手に使うと不正アクセス禁止法違反で逮捕される!
まずは、不正アクセス禁止法の概要と、制定された背景について確認しておきましょう。
そもそも不正アクセス禁止法とは?わかりやすく解説
不正アクセス禁止法とは、他人のIDやパスワードを無断で使用してシステムに侵入する行為や、それに関連する情報の不正な取得・保管、または不正アクセスを助けるような行為を禁じる法律です。
不正アクセスとは、簡単に言うと「本来は利用する権限がないにもかかわらず、不正な手段で権限を得て情報にアクセスすること」を意味します。
たとえば、他人のIDやパスワードをこっそり見てログインしたり、自分以外の人のアカウント情報を使ってメールやSNSに勝手にアクセスしたりする行為が該当します。
たとえ夫婦や家族といった親しい関係であっても、不正アクセスとみなされれば法律に違反することになるので、注意が必要です。
不正アクセス禁止法が制定された背景と目的
2000年頃に、インターネットの利用が急速に広がり始めた一方で、他人のIDやパスワードを使ってネットワークに侵入するような行為も問題となっていました。
こうした不正行為を取り締まり、インターネット上の秩序と安全を確保する必要が高まっていたのです。
このような背景を受けて、2000年に不正アクセス禁止法が施行されました。
不正アクセス禁止法の主な目的は、以下の3点です。
- 電気通信回線を通じておこなわれる電子計算機に係る犯罪の防止
- アクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持
- 高度情報通信社会の健全な発展への寄与
不正アクセス禁止法は、ネット社会を安心して利用できる環境を整えるために重要な役割を担っています。
不正アクセス禁止法違反として逮捕される行為と罰則
不正アクセス禁止法では、インターネット上の不正行為を5つの違反類型に分け、それぞれに対して罰則を定めています。
- 不正アクセス罪
- 不正取得罪
- 不正助長罪
- 不正保管罪
- 不正入力要求罪
ここから、各類型の違反内容と、それぞれに科される罰則について解説します。
不正アクセス罪|3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
不正アクセス罪は、本来アクセス権限のない人物が不正にアクセスしたときに成立します。
たとえば、以下のような行為が対象となります。
- 他人のID・パスワードを使って正規の利用者になりすまし、システムにログインする行為
- サーバーやソフトウェアの脆弱性(セキュリティ上の欠陥)を突いて侵入する行為
- ウイルスやマルウェアを使って無断でコンピュータ内部にアクセスする行為
不正アクセス罪が成立すると、「3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」が科されます。
不正取得罪|1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
不正取得罪は、不正アクセスのために、他人の識別符号(IDやパスワードなど)を不正に取得したときに成立します。
たとえば、以下のような行為が対象となります。
- 同僚がパソコンにログインする様子を後ろからのぞき見する行為(ショルダーハッキング)
- 社員が、顧客のIDやパスワードを無断で確認する行為
不正取得罪が成立すると、「1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」が科されます。
不正助長罪|30万円以下の罰金
不正助長罪は、正当な理由がないのに、他人の識別符号を第三者に提供・共有した場合に成立します。
たとえば、以下のような行為が対象となります。
- 「このアカウントでログインしても大丈夫だよ」と他人のID・パスワードを渡す行為
- 他人のログイン情報を、本人の同意なく口頭で第三者に伝える行為
不正助長罪が成立すると、相手方に不正アクセス目的があると知っていた場合には、「1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」が科されます。
また、情報を渡した相手の目的を知らなかった場合でも、「30万円以下の罰金」が科される可能性があります。
不正保管罪|1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
不正保管罪は、不正アクセスの目的で、他人の識別符号を不正に保管している場合に成立します。
たとえば、以下のような行為が対象となります。
- インターネット掲示板などから取得したログイン情報を、自分のメモ帳やスマホに保存する行為
- 不正に取得したIDやパスワードを、パソコンやUSBメモリなどに保管する行為
不正保管罪が成立すると、「1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」が科されます。
不正入力要求罪|1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
不正入力要求罪は、他人にIDやパスワードの入力を不正に要求する行為に適用されます。
たとえば、以下のような行為が対象となります。
- 銀行や公的機関を装った偽サイト(フィッシングサイト)を作り、利用者にIDやパスワードを入力させる行為
- 「アカウントが停止されました」などと偽ってメールを送り、リンク先で情報を入力させる行為
不正入力要求罪が成立すると、「1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」が科せられます。
不正アクセス禁止法違反の時効
不正アクセス禁止法に違反した場合、公訴時効は「3年」と定められています。
つまり、不正アクセスをしてから3年が経過すれば、検察官はその行為について起訴することができなくなり、結果として罪に問われることはありません。
ただし、ここで注意すべきなのは「期間のカウントがいつから始まるのか」という点です。
複数回にわたって不正アクセスをおこなっていた場合には、それぞれの行為が独立した犯罪として扱われます。
そのため、最初の不正行為から3年が経っていたとしても、最後の不正行為から3年以内であれば、その分については依然として処罰の対象となるのです。
また、他人のIDやパスワードを不正に保管していたケースでは、保管し続けている限り「不正な状態が継続している」と判断される可能性があります。
この場合、時効は進行せずにいつまでも罪に問われるリスクが残ります。
仮にIDやパスワードを処分したとしても、「いつ、どのように処分したのか」「処分したことを証明できるか」といった点について、警察から詳しく事情を調べられることもあります。
そのため、「不正行為から3年経過しているから大丈夫」と、安易に判断しないようにしましょう。
不正アクセス禁止法違反による逮捕事例
ここでは、不正アクセス禁止法に違反して逮捕された事例を2つ紹介します。
携帯大手会社のシステムに不正ログインして通信回線を契約した
2025年2月、楽天モバイルのシステムに不正アクセスし、eSIMの通信回線を不正に契約したとして、中高生3人が不正アクセス禁止法違反などの疑いで逮捕されました。
3人は、匿名性の高い通信アプリ「テレグラム」で知り合った人物から、約33億件にも及ぶID・パスワードの情報を購入していました。
購入した情報をもとに、独自のプログラムを用いて楽天モバイルのシステムにログインして、eSIM回線を合計105件不正に契約していたとされています。
また、約22万件のID・パスワードについて、実際にログインを試みた形跡が確認されました。
使用されたプログラムは、生成AI「ChatGPT」を活用し、パスワードを機械的に入力しながら回線契約まで自動でおこなう高度なもので、高校生の1人が独学で開発したものでした。
このプログラムを3人で共有し、不正契約を繰り返していたとみられています。
【参考】逮捕の中高生3人、楽天モバイルに不正アクセス22万件「高度な手口を投稿し注目集めたかった」|読売新聞
不正に入手したIDで他人のSNSにログインし、アカウントを乗っ取った
2023年1月、Instagramのアカウントを不正に乗っ取ったとして、茨城県牛久市の28歳の派遣社員の男性が、不正アクセス禁止法違反などの疑いで逮捕されました。
男性は、2020年8月から2021年10月にかけて、東京都や埼玉県、神奈川県などに住む20代女性9人のInstagramアカウントに合計59回ログインしました。
IDとパスワードを不正に取得し、パスワードを書き換えるなどしてアカウントを乗っ取ったとされています。
男性は、女性たちのSNS投稿から誕生日を推測し、それをアカウント名などと組み合わせてパスワードを割り出していたとみられています。
また、乗っ取ったアカウントを使って別の女性にダイレクトメッセージ(DM)を送り、パスワードを聞き出してさらにアカウントを不正取得していたようです。
本件は、2020年8月に被害女性の1人が「インスタにログインできない」と警察に相談したことをきっかけに発覚しました。
【参考】「リア充の20代女性に嫉妬して」 インスタ乗っ取り容疑で男を逮捕|朝日新聞
不正アクセス禁止法違反で逮捕されたあとの基本的な流れ
不正アクセス禁止法違反で逮捕・勾留された場合された場合、基本的には以下のような流れで刑事手続きが進みます。
- 警察で取り調べを受ける
- 検察へ送致され勾留が請求される
- 勾留され、その間に検察にて起訴・不起訴が決定される
- 刑事裁判を受ける
ここから、それぞれの手続きを時系列に沿って解説します。
【逮捕後48時間以内】警察で取り調べを受ける
不正アクセス禁止法違反の疑いで逮捕されると、まず警察によって取り調べがおこなわれます。
警察は、被疑者の身柄を逮捕から48時間以内に検察官へ送致しなければなりません。
そのため、警察は48時間以内に取り調べを集中的に進め、事件の概要を整理します。
この段階では、当番弁護士制度を利用して無料で一度だけ弁護士との面会が可能です。
ただし、継続的な支援を受けるには、私選弁護士への依頼が必要となります。
ここで弁護士に依頼しておけば、取り調べへの対応に関するアドバイスをもらるでしょう。
【逮捕後72時間以内】検察へ送致され勾留(留置場での身柄拘束)が請求される
警察での取り調べが終わると、被疑者の身柄は検察庁へ送致されることが多いです。
検察庁への送検は、逮捕から48時間以内におこなわれます。
そのあと、検察官が「被疑者を引き続き身柄を拘束して取り調べる必要がある」と判断した場合には、送検から24時間以内かつ逮捕から72時間以内に、裁判官へ勾留請求がおこなわれます。
勾留とは、証拠隠滅や逃亡を防ぐために、引き続き被疑者の身柄を拘束しておく措置です。
この時点で弁護士に依頼しておけば、勾留の必要がないことを裁判所に主張・立証してもらうなど、勾留の回避や早期の身柄解放を目指す弁護活動を受けられます。
【最大20日期間】勾留され、その間に検察にて起訴・不起訴が決定される
裁判所により勾留が認められると、留置場で身柄を拘束されることになります。
勾留期間は原則として10日間です。
ただし、検察官が取り調べなどにさらに時間が必要と判断した場合には、裁判所に申請することで最長10日間の延長が認められます。
つまり、最大で検察官が勾留請求をした日から20日間、身柄を拘束されたまま捜査を受ける可能性があります。
この勾留期間中に、検察官は起訴するか不起訴とするかを判断します。
不起訴処分となれば、被疑者はただちに釈放され、前科もつきません。
一方で、起訴された場合は裁判に進みます。
日本では有罪率が99.9%と非常に高いため、何らかの処罰を受けるケースがほとんどです。
この時点で弁護士に依頼しておけば、勾留の取消しや準抗告といった手続きを通じて、勾留の回避や早期の身柄解放を目指した弁護活動を受けられます。
【起訴から約1ヵ月後】刑事裁判を受ける
検察官が起訴を決定すると、被疑者は被告人として刑事裁判を受けます。
起訴後も原則として勾留は継続されるため、身柄を拘束された状態のまま裁判の日を待つことになります。
初公判が開かれるまでには、通常、起訴からおよそ1ヵ月ほどかかるのが一般的です。
ただし、この段階でも保釈請求が認められれば、公判開始前に身柄が解放される可能性があります。
刑事裁判では、弁護士が被告人の立場に立ち、執行猶予付きの判決や減刑を目指して、積極的な弁護活動をおこないます。
不正アクセスによる逮捕に関してよくある質問
ここでは、不正アクセスによる逮捕に関するよくある質問をまとめました。
気になるポイントがある方は、ぜひここで疑問を解消してください。
不正アクセスが発覚すると必ず逮捕される?
不正アクセスが発覚したからといって、必ず逮捕されるとは限りません。
逮捕が認められるのは、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」があるなど、刑事訴訟法上の要件を満たす場合に限られます。
実際、警察庁が公表した令和6年(2024年)のデータによれば、不正アクセスの認知件数は5,358件でしたが、検挙件数は563件にとどまり、検挙率は約11%です。
なお、「逮捕」と「検挙」は意味が異なる点には注意が必要です。
- 逮捕:身柄を拘束する強制的な手続き
- 検挙:警察が犯罪を犯した者を特定して捜査対象とすること
検挙したのちに被疑者を逮捕する場合もあれば、逮捕せず在宅処分や微罪処分とするケースもあります。
そのため、検挙された全てのケースで逮捕されるわけではないので、実際の逮捕率はさらに少ないと考えられます。
不正アクセス禁止法違反は親告罪?
不正アクセス禁止法は親告罪ではなく、「非親告罪」に分類されます。
つまり、被害者が警察に告訴していなくても、警察が不正アクセスの事実を把握した時点で捜査が開始される可能性があります。
さいごに|不正アクセスによる逮捕のおそれがあるなら弁護士に相談を!
本記事では、不正アクセス禁止法違反についてわかりやすく解説しました。
たとえ軽い気持ちや悪意のない行為だったとしても、他人のIDやパスワードを無断で使用すれば、不正アクセス禁止法に違反したと判断され、逮捕される可能性があります。
逮捕や実刑判決といった事態を防ぐためには、刑事事件を得意とする弁護士に早めに相談することが大切です。
弁護士に相談すれば、取調べへの対応方法に関するアドバイスや、勾留の回避、不起訴処分に向けた主張・立証、または被害者との示談交渉など、状況に応じた適切なサポートを受けられます。
ベンナビ刑事事件では、不正アクセスを含む各種刑事事件を得意とする弁護士を、お住まいの地域に応じて簡単に探せます。
不安な気持ちが少しでもあれば、ひとりで抱え込まず、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。