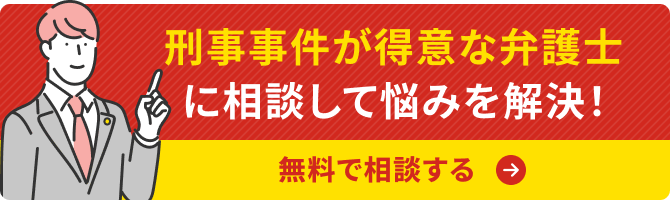- 「検察の取り調べは厳しいって本当?」
- 「どう対応すればいいのかわからない…」
警察の取り調べを経て、このような不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
検察による取り調べは、警察の取り調べとは異なり、起訴・不起訴の判断にも影響します。
そのため、供述内容によっては不利な状況に追い込まれてしまうこともあり、特に初めて経験する方にとっては、精神的にも大きな負担となりがちです。
そこで本記事では、検察の取り調べがどのようにおこなわれるのか、取り調べが厳しくなりやすいケースや不当に厳しい取り調べを受けた際の対処法についてわかりやすく解説します。
ご自身やご家族の身を守るために、正しい知識を身につけておきましょう。
検察の取り調べは厳しい?
結論からいうと、検察官による取り調べはさほど厳しくありません。
基本的には、被疑者の話にきちんと耳を傾けてくれます。
その背景には、2019年6月1日に施行された改正刑事訴訟法の影響があります。
この法改正では、裁判員裁判の対象事件と検察官独自捜査事件では、取り調べの様子を最初から最後まで録音・録画することが義務づけられました。
その後、検察庁の運用としては、身柄事件(逮捕・勾留された場合)については基本的に全ての事件で録音・録画を実施しており、2025年4月からは在宅事件で起訴見込みの事案での録音録画の試行が始まりました。
録音・録画によって取り調べの様子が可視化されるようになったので、不適切な言動が記録に残らないよう、より丁寧で慎重な取り調べがおこなわれるようになりました。
また、検察官による取り調べは、被疑者を起訴するかどうかの判断のために、被疑者の反省の態度や示談の成立状況、家族からの支援など、被疑者にとって有利な事情も確認されます。
そのため、警察官の取り調べと比較すると、検察官の取り調べは厳しくならないことが多いのです。
ただし、全ての取り調べが適正におこなわれているとは限りません。
実際に、検察官から不適切な言動や侮辱的な発言を受けた事例も報告されています。
検察の取り調べが厳しくなりやすい3つのケース
検察の取り調べは通常はそこまで厳しくありませんが、以下3つのケースに該当すると、取り調べが厳しくなる傾向があります。
- 被疑者が容疑を否認している場合
- 被疑者が黙秘権を行使している場合
- 客観的な証拠が乏しく、自白の重要性が高まっている場合
それぞれのケースについて、詳しく見ていきましょう。
1.被疑者が容疑を否認している場合
被疑者が容疑を否認している場合は、取り調べが厳しくなりやすいです。
検察が刑事事件で被告人を有罪とするためには、「被告人が罪を犯したことに疑いの余地がない程度」にまで立証しなければなりません。
しかし、容疑を否認されると事実認定が難しくなるので、検察官は疑問点を徹底的に追及します。
その結果、厳しい取り調べをおこなうに至るケースがあるのです。
なお、明らかな証拠が揃っているにもかかわらず容疑を否認し続けていると、検察官や裁判官に「反省していない」と受け取られ、悪印象を持たれる可能性があります。
そのため、取り調べで否認を貫くかどうかは、取り調べを受ける前に弁護士に相談し、慎重に検討しましょう。
2.被疑者が黙秘権を行使している場合
被疑者が黙秘権を行使している場合も、取り調べが厳しくなりやすいです。
黙秘権とは、取り調べ中に言いたくないことは言わなくてもよいという、憲法で認められた権利です。
検察官は、黙秘権を行使する被疑者に対して、無理に話をさせることはできません。
しかし、黙秘権を行使しても検察は取り調べを中断せず、話を引き出そうと説得を続けることが一般的です。
そのため、自然と取り調べが厳しくなったり、取り調べの時間や回数が増えたりすることがあります。
どこまで黙秘権を行使すべきか悩むときは、取り調べを受ける前に弁護士に相談し、自分にとって適切な対応を確認しておくのがおすすめです。
3.客観的な証拠が乏しく、自白の重要性が高まっている場合
客観的な証拠が乏しい場合にも、取り調べが厳しくなりやすいです。
刑事事件では、物的証拠や証人による証言など、客観的な証拠による事実関係の裏づけが欠かせません。
しかし、取り調べの時点で証拠が十分に揃っていない場合には、被疑者の自白に頼らざるを得なくなります。
自白とは、被疑者自身が不利な事実を認める発言をいいます。
自白が起訴の判断や裁判での事実認定に大きく影響する場合、検察官が自白を得ようとして取り調べを厳しくする可能性があるでしょう。
また、本来はこうあってはならないのですが、自白を得るために、身柄拘束の延長や、繰り返しの取り調べがおこなわれることもあります。
【事例付き】検察でおこなわれる厳しい取り調べの具体例3選
ここでは、検察による厳しい取り調べが問題となった事例を3つ紹介します。
1.脅迫的な言動などがおこなわれる
Aさんは、未成熟子を出産後、必要な措置をとらずに死なせたという保護責任者遺棄致死の嫌疑で、逮捕・勾留されました。
Aさんは、取り調べで黙秘を貫いていましたが、取り調べを担当した検察官は、Aさんに対して「亡くなった赤ちゃんに対する罪の意識はないのか」「仏壇に手を合わせられるのか」などと黙秘権の行使を不当に妨害する発言を用いて、供述するよう強く迫りました。
その後、Aさんは取り調べの状況について弁護人に相談しました。
取り調べは録音・録画されていたため、弁護人は取り調べ記録映像を視聴し、不当な発言が実際におこなわれていたことを確認しました。
そして、弁護人は検察官の捜査を監督する立場にある担当検察庁の検事正宛てに苦情を申し出るとともに、Aさんに対する取り調べの状況についての調査を求めました。
その結果、検察庁から回答があり、検察官が当該発言をおこなった事実は認められましたが、「供述を促すための説得の範囲にとどまるものであり、問題はないと判断している」という内容でした。
2.共犯者の手紙を使って自白を迫られる
車上荒らし(窃盗)の容疑で逮捕・勾留されたBさんは、取り調べに対して一貫して黙秘を貫きました。
しかし、取り調べを担当した検察官は、Bさんと同じ事件に関係する人物であるCさんのもとを訪れ、Bさん宛ての手紙を書かせ、その手紙を証拠品として預かりました。
その後、取り調べの際、Bさんに対して「私が接見禁止をつけたのに、手紙というのは本来あり得ない話だけど、Cさんがどうしてもと言うので、とりあえず証拠品として採用しました。
その中から私が抜粋したものを読み上げます」と述べ、Cさんが書いた手紙の内容を読み上げました。
内容は、「自分の口から責任を取れ」「検事に素直に話したほうがいい」といった、供述を強く促すものでした。
このような取り調べを受けたことをBさんが弁護人に相談したことをきっかけに、弁護人は、検察官の取り調べを監督する立場にある担当検察庁の検事正に対し苦情の申立てをおこなうとともに、取り調べの方法の改善を求めました。
申立てに対する回答はありませんでしたが、最終的にAさんは不起訴処分となりました。
3.長期間かつ長時間の取り調べがおこなわれる
弁護士であったDさんは、交通事故に関する事件で犯人隠避を教唆したという疑いをかけられ、検察庁に逮捕されました。
Dさんは、逮捕直後から一貫して黙秘権を行使する意思を表明していました。
しかし、Dさんが黙秘を続けるなか、取り調べを担当した検察官は、22日間にわたり50時間以上もの取り調べをおこないました。
そして、取り調べ中に以下のような人格を傷つけるような発言を繰り返しました。
| 「お子ちゃま発想だったんでしょうね、あなたの弁護士観っていうのはね。全然大間違いですよ。ガキだよねあなたって。なんかね、子どもなんだよね。子どもが大きくなっちゃったみたいなね。」 「本質を見ようとする能力、努力、いずれも足りなかったからですよね。全てが場当たり的。で、しかもちょっと歪んじゃっているわけですよね。」 「超筋悪ですね。まさに刑事弁護を趣味でしかやれない人。プロではない。」 「ある意味弁護士としての能力が相当程度劣っているあなたの弁護活動を、なんだか知らないけど弁護士っていう肩書きがあるもんだから、あれなんとなく信用できるかしらって関わっちゃった人たちが、おかしな弁護活動されて、権利義務についての重大な場面でひどい目に遭って。」 「素質的にも刑事弁護やる資格はないんすよ。刑事弁護だけじゃなくて弁護士自体、資格がないんですよ。あなたには。なかったんですよ。」 |
Dさんは、取り調べにより黙秘権・弁護権・人格権が侵害されたとして国家賠償請求訴訟を提起しました。
その結果、東京地方裁判所は2024年7月18日の判決において、当該取り調べは違法と認定しました。
検察から厳しい取り調べを受けたときに弁護士に相談すべき3つの理由
検察官からの取り調べが精神的に辛い、威圧的な言葉で追い詰められた場合には、まず弁護士に相談することが大切です。
弁護士に相談することで、以下のようなサポートを受けられます。
1.検察に対して苦情の申し入れをしてくれる
弁護士は、不当な取り調べが続かないよう、検察庁に対して正式に改善を求める申し入れをおこない、取り調べの改善を要求してくれます。
これにより、今後の取り調べが適正なものとなることが期待できます。
2.今後の取り調べに関するアドバイスがもらえる
弁護士に相談すれば、取り調べにどのように対応すればよいか具体的なアドバイスを受けられます。
取り調べで話した内容は供述調書に記録され、裁判で証拠として使用されます。
つまり、取り調べで話す内容は後の処分や裁判に大きな影響を与える可能性があるということです。
しかし、ほとんどの人は初めて取り調べというものを経験するうえ、突然の取り調べでは不安のあまり不利な発言をしてしまうかもしれません。
その点、弁護士は具体的状況をふまえたうえで、「黙秘するべきか」「どのように答えるべきか」などを教えてくれます。
3.悪質な取り調べには国家賠償請求をしてくれる
検察官による取り調べには、違法または不当な行為が含まれることがあります。
そのような取り調べによって精神的苦痛や不当な拘束を受けた場合、国に対して損害賠償を請求することが可能です。
ただし、損害賠償請求のためには、取り調べの違法性を示す証拠や、法的根拠に基づいた立証が必要です。
素人が自力で国を訴えようとしても、適切な方法がわからずに泣き寝入りせざるえないでしょう。
その点、弁護士であれば、取り調べの録音・録画データや供述記録などを精査し、適切に手続きを進めることができます。
さいごに|検察に厳しい取り調べをされたら早めに弁護士に相談しよう
検察による取り調べが厳しいと感じたときは、ひとりで抱え込まず、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談すれば、取り調べの適正性を判断してもらえるだけでなく、検察への申し入れや今後の対応についてアドバイスも受けられます。
違法な取り調べがあれば、国家賠償請求による責任追及も可能です。
なお、刑事事件では、被告人は弁護士を「国選弁護人」と「私選弁護人」の2種類から選べます。
国選弁護人は、費用負担が少なく済む点がメリットですが、担当する弁護士を自分で選ぶことはできません。
一方で、私選弁護人であれば自分に合った弁護士を自由に選べるほか、勾留前の早い段階から弁護を依頼できます。
また、在宅事件では、国選弁護人が就くことはできないため、弁護士のサポートを受けるには私選弁護人に依頼する必要があります。
「ベンナビ刑事事件」を利用すれば、事件の内容やお住まいの地域に合った私選弁護人を簡単に探せます。
自分にとって信頼できる弁護士を早めに見つけるためにも、ぜひご活用ください。