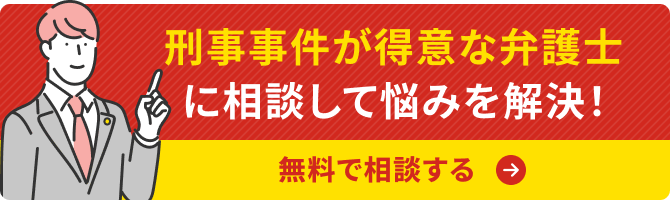「駅から家まで歩くのが面倒だった」「少しだけ借りるつもりだった」といった軽い気持ちであっても、他人の自転車を無断で使用すると、窃盗罪に問われる可能性があります。
「バレなければ大丈夫」と考える方もいるかもしれませんが、警察に発覚すれば刑事事件として処理され、たとえ初犯であっても、逮捕や起訴、さらには前科がつくおそれもあるため、決して軽く考えてはいけません。
本記事では、自転車窃盗が発覚した場合に処罰される可能性や刑罰の内容、手続きの流れ、加害者がとるべき適切な対応について解説します。
自転車を窃盗・盗難に関する基礎知識|自転車盗は窃盗の中で最も多い!
窃盗罪の中で、もっとも認知件数が多いのは「自転車盗」です。
法務省が公表した「令和6年版 犯罪白書」によると、令和5年の窃盗事件全体の認知件数は48万3,695件でした。
そのうち自転車盗は16万4,180件と、全体の約34%を占めています。
つまり、3件に1件以上が自転車盗に関する事件にあたります。
しかし、自転車盗の検挙件数は1万989件で、検挙率でいえば約6.7%です。
一般的な犯罪全体の平均検挙率は約40%前後であることを踏まえると、自転車盗での検挙率は極めて低いといえます。
| 認知件数 | 約16万3,972件 |
|---|---|
| 検挙件数 | 約1万998件 |
| 検挙率 | 約6.7% |
【参考元】法務省|令和6年版 犯罪白書 第1編/第1章/第2節/1
検挙率が低い背景には、自転車盗は周囲から犯罪と認識されにくいという点が挙げられます。
たとえば、鍵のかかっていない自転車を持ち出しても、通行人からは所有者本人が利用しているように見えることが多く、不審に思われづらいのです。
しかし、防犯カメラの映像や目撃証言などによって犯人が特定され、後日検挙されるケースも実際に存在します。
自転車盗が決して発覚しないわけではない、ということをしっかり認識しておきましょう。
自転車の窃盗・盗難は犯罪!問われる主な罪の種類と刑罰
自転車の窃盗や盗難が発覚すると、「窃盗罪」や「遺失物横領罪」などに問われます。
ここから、それぞれの犯罪について詳しく解説します。
1.窃盗罪|10年以下の懲役または50万円以下の罰金
他人の自転車を盗むと、窃盗罪が成立する可能性があります。
罰則は「10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です。
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法 | e-Gov 法令検索
窃盗罪の成立要件は、以下の4つです。
- 対象物を他人が占有していること
- 占有者の意思に反して、対象物を自己または第三者の占有に移転すること(窃取すること)
- 犯罪の故意(盗む意思)があること
- 不法領得の意思(権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用または処分する意思)があること
たとえば、駐輪場に止められている自転車を盗んだケースなどが該当します。
2.遺失物等横領罪|1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料
長期間放置された自転車を勝手に持ち帰ると、遺失物等横領罪が成立する可能性があります。
罰則は「1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料(1,000円以上1万円未満の財産刑)」です。
(遺失物等横領)
第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
引用元:刑法 | e-Gov 法令検索
遺失物等横領罪の成立要件は、以下の3つです。
- 対象物が占有離脱物(所有者の占有を離れた物)であること
- 対象物が他人の所有物であること
- 横領すること(不法領得の意思の発現となる行為をすること
- つまり、権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様に、その経済的用法に従いこれを利用または処分する意思の現れである行為をすること)
- 犯罪の故意(横領する意思)があること
たとえば、所有者が乗り捨てた放置自転車を盗んだケースや、所有者から盗まれた後の放置自転車に乗って使用したケースなどが該当します。
自転車の窃盗・盗難が発覚したあとの流れ|逮捕や起訴のリスクもある
自転車の窃盗・盗難が被害者に発覚すると、一般的には以下のような流れで手続きが進みます。
- 被害者が被害届を提出する
- 警察によって逮捕される
- 検察に事件が送致される
- 必要に応じて勾留される
- 検察が起訴・不起訴の判断をする
ここから、それぞれのステップについて詳しく解説します。
1.被害者が被害届を提出する
まずは、自転車を盗まれた被害者が警察に被害届を提出します。
これにより警察は事件を正式に認知し、捜査を開始します。
2.警察によって逮捕される
容疑者が特定されると、警察に逮捕される可能性があります。
自転車盗では、現行犯で逮捕されることが多いです。
たとえば、盗難自転車に乗っていたときに職務質問されるケースや、実際に盗んでいる現場を目撃されたケースなどが該当します。
一方で、防犯カメラの映像や目撃証言、被害届の内容などから、後日逮捕されるケースもあります。
逮捕されたあとに実施されるのは取り調べです。
逮捕後の取り調べは身柄拘束から最大48時間にわたっておこなわれ、犯罪を行ったかの認否、犯行の経緯や動機、反省の有無などについて詳しく聞かれます。
ただし、以下のようなケースでは、逮捕されずに「在宅事件」として取り扱われる可能性があります。
- 被害金額が少ない
- 本人が罪を認めている
- 逃亡や証拠隠滅のおそれがない
在宅事件として処理されると、身柄を拘束されることはなく、普段通りの生活を送りながら捜査を受けます。
ただし、警察や検察からの呼び出しがなされることがあり、これは任意ですが、応じなければ逮捕される可能性が生じるのが実情です。
3.検察に事件が送致される
警察の取り調べが終わると、検察に事件が送致されます。
検察官は、警察から送付された書類や証拠を確認し、必要に応じて追加の取り調べをおこないます。
ただし、被害の程度や犯行の内容によっては、「微罪処分」として処理される場合があります。
微罪処分とは、一定の軽微な犯罪について、警察官の判断で事件を終結させる処分のことです。
微罪処分になると、検察に事件は送致されません。
その代わりに、被疑者本人に訓戒を加えるとともに親などの監督者に指導をおこない、今後の監督を誓約する書面を提出してもらうといった対応がとられます。
4.必要に応じて勾留される
事件が検察に送致されたあとは、検察が送致を受けた時から24時間以内かつ身柄拘束時から72時間以内に勾留の必要性を判断します。
勾留とは、逃亡や証拠隠滅を防ぐために身柄を拘束する手続きのことです。
検察が勾留の必要があると判断した場合、裁判官に勾留請求をおこない、請求が認められれば勾留が開始されます。
勾留期間は最長で勾留の請求時から20日に及びます。
5.検察が起訴・不起訴の判断をする
勾留期間中または在宅事件として処理されている間に、検察官が「起訴」または「不起訴」の判断を下します。
起訴された場合は刑事裁判がおこなわれ、有罪が確定すると罰金刑や懲役刑などの刑罰が科されます。
不起訴となった場合はそれ以上の刑事手続きはおこなわれず、事件は終了します。
起訴するかどうかの判断にあたっては、犯罪の証明ができるか、被害者との示談の有無、反省の態度、前科の有無などが考慮されます。
なお、日本の刑事裁判の有罪率は非常に高く、起訴されるとその時点でほぼ有罪が確定してしまいます。
そのため、自転車の窃盗で捕まった場合は、不起訴処分を勝ち取るために早期に防御活動を展開することが大切です。
自転車の窃盗を理由に有罪判決を受けた事例2選
ここでは、自転車窃盗に関して有罪判決を受けた事例を2つ紹介します。
1.自転車盗を繰り返していた事例(懲役1年6ヵ月)
Aさん(37歳・無職)は、山口県防府市内で繰り返し自転車を盗んだとして、常習類犯としての窃盗罪に問われました。
Aさんは、自宅から職場までの移動に使っていた自転車がパンクし、徒歩で通勤することが負担になっていたことをきっかけに、無施錠の自転車を常習的に盗みました。
Aさんは以前にも窃盗で有罪判決を受けた経験がありましたが、直近7年間は同様の犯罪に手を染めていませんでした。
検察は、Aさんがこれまでに複数回の窃盗を繰り返していたことや、再犯のおそれが高いことを理由に、懲役3年の実刑を求刑しました。
弁護側は、Aさんが更生の意志を持ち、働く意欲もあることから、執行猶予付きの判決を求めて審理を終えました。
2023年6月14日の判決公判で、山口地裁の裁判官は「7年が経過していることを踏まえても、被告人の盗癖は根深い」「経済的に困窮した中での犯行というが身勝手な理由で酌量の余地に乏しい」などの理由から、懲役1年6ヵ月の実刑判決を言い渡しました。
【参考元】「徒歩通勤が体力的にしんどい」自転車盗を繰り返した男(37)…逮捕され、離婚し気付いた”妻と子の大切さ” | 山口のニュース・天気・防災|tys NEWS|tysテレビ山口 (1ページ)
2.自転車を元に戻したが12時間程度乗り回していた事例(懲役6ヵ月)
Bさん(25歳・無職)は、福岡市内の市営住宅の駐輪場に止められていた盗難車両の自転車を無断で使用したとして、占有離脱物横領の罪で起訴されました。
Bさんは、自転車を一時的に使用したのちに元の場所に戻していたという事実が何度かあったため、福岡地裁は「返還を前提とする一時的な無断借用に過ぎない」として、2020年9月に無罪判決を言い渡しました。
検察側は無罪判決を不服として控訴し、2021年3月、福岡高等裁判所で審理がおこなわれました。
高裁は、「数時間にわたり無断で使用することの可罰性を『一時的な無断使用』として否定することは、一般的な社会通念に反し、認められない」と認定して、懲役6ヵ月の有罪判決を言い渡しました。
【参考元】「返せば問題ないの?」放置自転車の無断使用、有罪・無罪の境界線はどこに : 読売新聞
自転車を窃盗した加害者がやるべき4つの対応
自転車の窃盗が発覚すると、場合によっては刑事責任を問われ、有罪判決を受ける可能性もあります。
起訴を避けたり、刑罰を軽減したりするためには、早い段階で適切な対応をとることが重要です。
ここでは、加害者が取るべき主な対応を4つ紹介します。
1.自首を検討する
自転車を盗んでしまい、警察に逮捕されることが不安なら、自首を検討しましょう。
自首とは、警察が事件を把握していない段階で、犯人が犯罪を申告することです。
自首することで、刑が軽くなる可能性が高まります。
また、自ら出頭していることから、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断され、逮捕を回避できる可能性も高くなります。
2.被害者との示談を成立させる
自転車を盗んだことがバレるか心配な場合は、被害者と示談をおこなうことも検討しましょう。
示談とは、加害者が被害者に対して金銭的な補償をおこない、事件を円満に解決することをいいます。
示談金の金額は、法律で決まっているわけではなく、被害者と弁護士との話し合いで決まります。
示談が成立している場合、警察や検察はすでに当事者間で問題が解決していると判断するため、不起訴となる可能性は高くなります。
また、事件が警察に発覚する前に示談が済んでいれば、逮捕を免れるケースもあるでしょう。
ただし、自転車窃盗では被害者と加害者が面識がないことが多く、加害者が被害者の連絡先を知るのは現実的に困難です。
仮に連絡先を知っていたとしても、加害者が直接連絡を取ると、かえってトラブルになるおそれもあります。
そのため、示談交渉は必ず弁護士を通じておこないましょう。
3.窃盗癖がある場合には治療を受ける
もしも自転車の窃盗癖があるなら、精神科・心療内科での治療やカウンセリングを受けることも検討すべきです。
窃盗を繰り返してしまう人は、衝動をコントロールできない「クレプトマニア」といった病気と診断される可能性があります。
放置すると再犯に至る可能性が高くなるので、早めに治療を行いましょう。
また、病気を治すには、周囲の理解や協力も欠かせません。
本人が回復に向けて努力しやすい環境を整えることが、再発防止につながります。
なお、治療を受けることで裁判所に対して「更生の意志がある」という意思を示せるので、処分が軽減される可能性もあります。
4.刑事事件が得意な弁護士に相談する
自転車を盗んでしまったときに何よりも大切なのが、刑事事件を得意とする弁護士への相談です。
弁護士に相談すれば、自首のタイミングを教えてくれるだけでなく、被害者との示談交渉も進めてくれます。
逮捕されてしまった場合や、警察や検察から呼び出しを受けている場合でも、今後の流れや処分の見通し、取り調べにどう対応すべきか専門的なアドバイスを受けられます。
さいごに|他人の自転車を無断で使用すれば窃盗罪が成立する可能性がある
他人の自転車を無断で使用すると、窃盗罪に問われる可能性があります。
捜査の対象となれば、逮捕や勾留を経て、刑事裁判で有罪判決が下されることもあり得ます。
刑事処分を回避するためには、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。
弁護士に相談することで、取り調べに対する適切な対応や、被害者との示談交渉、自首に関するアドバイスなど、あらゆる場面で専門的なサポートを受けられます。
なお、ベンナビ刑事事件を利用すれば、>窃盗事件を得意とする弁護士を簡単に探せます。
今後の人生に悪影響を残さないためにも、まずは弁護士に相談しましょう。