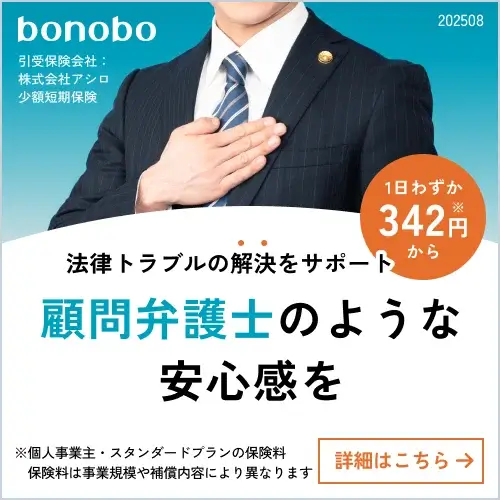- 弁護士保険の特徴とメリット|個人向け・事業者向けどちらにも共通する5つの項目
- 弁護士保険の補償範囲内の『特定偶発事故』と『一般事件』について
- 個人向け弁護士保険の保険金支払い事例10選
- 事業者向け弁護士保険の保険金支払い事例10選
- 【債権回収】納品した商品の代金を取引先が支払ってくれないケース
- 【労務問題】解雇した元従業員から「不当解雇」で訴えられたケース
- 【契約トラブル】業務委託先が納期を守らず、プロジェクトに損害が出たケース
- 【不動産トラブル】賃貸している店舗のテナントが家賃を滞納しているケース
- 【知的財産権】競合他社に自社のウェブサイトのデザインを模倣されたケース
- 【カスタマーハラスメント】顧客から執拗なクレームと土下座を要求されたケース
- 【風評被害対策】インターネット掲示板に根拠のない悪評を書き込まれたケース
- 【下請法違反】元請け企業から一方的な代金の減額を要求されたケース
- 【情報漏洩】業務委託先のミスで顧客情報が流出してしまったケース
- 【施設賠償】店舗内で顧客が転倒し、安全管理体制を問われたケース
- 弁護士保険に加入する10のメリットと副次的な効果
- 弁護士保険のデメリットは何か?
- 弁護士保険への加入条件として設けられている主な項目
- 弁護士保険の補償対象者
- 待機期間と不担保期間を知っておこう
- 主要な弁護士保険会社を比較
- 弁護士保険の加入がおすすめの方
- 弁護士保険に関するよくある質問
- さいごに
弁護士保険(弁護士費用保険)とは、思いがけない法的なトラブルに遭遇した際、弁護士への相談料や依頼にかかる着手金、報酬金といった費用を補償してくれる保険です。「転ばぬ先の杖」として、金銭的な不安なく専門家である弁護士にアクセスできることを目的としています。
この弁護士保険は、大きく「個人向け」と「事業者向け」の2種類に分けられ、それぞれ補償の対象となるトラブルの範囲が異なります。
【個人向け】
個人やそのご家族の日常生活におけるトラブルが対象です。具体的には、離婚や相続といった親族間の問題、騒音などのご近所トラブル、パワハラやセクハラなどの労働問題、ネットでの誹謗中傷、お子様のいじめ問題まで、幅広いリスクに備えることができます。
【事業者向け】
法人や個人事業主の事業活動に伴う法的なトラブルを対象とします。例えば、取引先からの売掛金未回収、顧客からの不当なクレーム(カスタマーハラスメント)、従業員との労務問題、著作権などの知的財産権の侵害といった、事業運営に直結する多様なリスクをカバーします。
このように、ご自身の立場(個人か事業者か)と、どのようなリスクに備えたいかを明確にすることが、適切な弁護士保険を選ぶ上で最も重要です。法的トラブルは誰にでも起こりうるもの。この保険は、泣き寝入りを防ぎ、ご自身の権利を守るための有効な備えと言えるでしょう。
基本的には弁護士費用がかかることを懸念し、なかなか相談できないというケースも多いのではないでしょうか。弁護士保険は法律トラブルに巻き込まれたときに弁護士費用を補償してくれる保険として、加入する大きなメリットがあると言えます。
本記事では、弁護士費用保険に加入する条件や補償内容、メリットとデメリットなどを解説します。
弁護士保険の特徴とメリット|個人向け・事業者向けどちらにも共通する5つの項目
個人向け・事業者向けに共通する5つの大きな特徴を、それぞれ詳しく解説します。
予防法務としての機能(トラブルの早期解決・未然防止)
弁護士保険の最も重要な価値の一つは、トラブルが深刻化する前にその芽を摘む「予防法務」としての機能です。通常、弁護士への相談は「大事になってから」と考えがちですが、その背景には「相談だけで費用が発生する」という金銭的なハードルがあります。
しかし、弁護士保険に加入していれば、多くの場合、法律相談料も補償の対象となるため、問題の初期段階でためらうことなく専門家の助言を仰ぐことができます。
例えば、個人であればご近所との些細な意見の食い違い、事業者であれば取引先との契約内容に関する小さな疑問点など、違和感を覚えた時点ですぐに弁護士に相談できます。早期に相談することで、法的に有利な証拠の残し方や、相手方との適切な交渉方法についてアドバイスを受けられ、紛争への発展を未然に防ぐことが可能になります。
仮に紛争に発展したとしても、初期対応が適切であれば、その後の展開を有利に進めやすくなります。このように、弁護士保険は単なる事後処理の費用補償に留まらず、トラブルそのものを回避・軽減させるための強力なツールとして機能するのです。
弁護士へのアクセス障壁の低減
多くの人々が法的なトラブルを抱えても弁護士への相談をためらう理由は、大きく分けて「費用の壁」と「心理的な壁」の2つが存在します。弁護士保険は、この両方の壁を取り払う上で絶大な効果を発揮します。
まず「費用の壁」について、弁護士費用は高額であるというイメージが先行し、「いくらかかるか分からない」という不透明さが相談への大きな足かせとなっています。弁護士保険は、この費用を保険でカバーできるという安心感を提供し、経済的な理由で相談を諦める必要をなくします。
次に「心理的な壁」ですが、「こんなことで相談して良いのだろうか」「そもそも知り合いに弁護士がいない」といった精神的なハードルも決して低くありません。保険に加入しているという事実は、「保険を使えるのだから相談して当然だ」という心理的な後押しになります。
さらに、ほとんどの保険には、相談内容に応じて最適な弁護士を無料で紹介してくれるサービスが付帯しています。これにより、「誰に相談すればよいか」という悩みも解消され、弁護士という存在を「かかりつけ医」のように、より身近で頼れる専門家として活用できるようになるのです。
費用倒れのリスクをなくし、泣き寝入りを防ぐ
「費用倒れ」とは、裁判などで勝訴して得られる経済的利益よりも、弁護士に支払う費用の方が高くなってしまう状態を指します。
この費用倒れを恐れるあまり、本来主張できるはずの正当な権利を諦めてしまう「泣き寝入り」が、社会には数多く存在します。弁護士保険は、この問題を解決するための極めて有効な手段です。
例えば、個人であれば「大家が敷金を5万円しか返してくれない」、事業者であれば「取引先が15万円の売掛金を支払ってくれない」といった少額のトラブルが典型例です。これらのケースで弁護士に依頼すれば、費用倒れになる可能性が高いため、多くの人は「仕方ない」と諦めてしまいがちです。
しかし、弁護士保険に加入していれば、弁護士費用は保険から支払われるため、自己負担を心配することなく、少額の請求であっても臆することなく法的手段を講じることができます。
これは、金額の大小にかかわらず、法の下では誰もが平等に権利を主張できるという原則を実質的に支えるものです。泣き寝入りを一つでも減らし、公正な社会を実現するためにも、弁護士保険が果たす経済的な支えとしての役割は非常に大きいと言えます。
弁護士紹介などの付帯サービスの充実
弁護士保険の価値は、単に弁護士費用を金銭的に補償するだけではありません。トラブルに直面した契約者が、実際に問題を解決するまでの道のりをスムーズに進めるための、手厚い「付帯サービス」が充実している点も大きな特徴です。その中でも特に重要なのが「弁護士紹介サービス」です。
いざ弁護士に相談しようと思っても、世の中に数多くいる弁護士の中から、自分の抱えるトラブルの分野(相続、労働問題、IT、不動産など)に精通した、信頼できる専門家を自力で探し出すのは至難の業です。
弁護士紹介サービスを利用すれば、保険会社が提携する弁護士ネットワークの中から、相談内容に最も適した弁護士を無料で紹介してくれます。これにより、弁護士探しの手間や時間を大幅に節約し、迅速に問題解決に着手することが可能になります。
また、保険会社によっては、弁護士に正式に依頼する前の段階で、電話による無料の法律相談サービスを提供している場合もあります。これにより、そもそも弁護士に依頼すべき事案なのか、どのような解決策が考えられるのかといった初期的な見立てを得ることができ、契約者の安心に繋がります。
保険金が支払われない「免責事由」の存在
弁護士保険は非常に心強い備えですが、あらゆるトラブルで無条件に保険金が支払われるわけではありません。プロの視点から最も強調したいのは、保険金支払いの対象外となる「免責事由」が必ず定められているという点です。
これを契約前に正しく理解しておくことが、いざという時に「使えると思っていたのに使えない」という事態を避けるために不可欠です。
個人向け・事業者向けに共通する代表的な免責事由には、まず「故意または重大な過失による法令違反」に起因するトラブルが挙げられます。例えば、自らが行った詐欺行為や犯罪行為に関する弁護費用は対象外です。また、「保険契約前に既に発生していたトラブル(既発紛争)」や、そのトラブルの発生が予測されていた場合も補償されません。保険はあくまで将来の予測できないリスクに備えるものだからです。
その他、地震や噴火といった天災、戦争や暴動などが原因の紛争も一般的に免責となります。さらに、各保険商品によって個別の免責事由(例:特許出願そのものにかかる費用、離婚の一部など)も細かく定められています。
ご自身の備えたいリスクが補償の対象内か、契約前に約款をしっかりと確認することが賢い保険活用の第一歩です。
弁護士保険の補償範囲内の『特定偶発事故』と『一般事件』について
弁護士保険の補償範囲を理解する上で非常に重要な『特定偶発事故』と『一般事件』について、それぞれ詳しく解説します。
特定偶発事故とは
『特定偶発事故』とは、個人の日常生活において、予期せず突発的に発生した身体の傷害や財物の損壊を伴う事故を指します。
このカテゴリの最大の特徴は、原因が「急激かつ偶然な外来の事故」である点にあります。自動車事故、自転車での衝突事故、スポーツ中の怪我、他人のペットに噛まれた、他人の物を誤って壊してしまった、といった具体的なトラブルがこれに該当します。
例えば、あなたが交通事故の被害に遭い、加害者側の保険会社が提示する示談金に納得できない場合、弁護士に交渉を依頼する費用が補償の対象となります。このとき、事故の発生日が保険期間中であることが絶対条件です。
補償の範囲は、加害者への損害賠償請求や、不当に高額な賠償を請求された場合の防御活動にかかる弁護士費用が中心です。保険金の支払い上限額は、後述の『一般事件』よりも高く設定されていることが多く、これは事故による損害が多額になりやすいことを考慮しているためです。
ただし、離婚や相続、労働問題といった事故性のないトラブルは、たとえ精神的な苦痛を伴うものであっても『特定偶発事故』には含まれません。あくまで物理的な事故が起点となる法的トラブルに特化した補償範囲と理解してください。
一般事件とは
『一般事件』とは、特定偶発事故に該当しない、広範な法的トラブル全般を指します。こちらの特徴は、事故性を問わず、日常生活や事業活動の中で生じる多種多様な権利侵害や契約上の紛争をカバーする点にあります。
個人向け保険であれば、離婚(慰謝料・財産分与)、相続(遺産分割協議)、労働問題(不当解雇・残業代未払い)、近隣トラブル(騒音問題)、インターネット上の誹謗中傷、金銭貸借トラブル、敷金返還トラブルなどが典型例です。これらは突発的な事故ではなく、人間関係や契約関係の中からじわじわと発生する問題です。
事業者向け保険では、売掛金の未回収、取引先との契約不履行、従業員との労務紛争、カスタマーハラスメントへの対応などが含まれます。
『一般事件』の補償は、弁護士保険の真価が最も発揮される部分と言えるでしょう。
特定偶発事故に比べて発生頻度が高く、多くの人が「泣き寝入り」しがちなトラブルだからです。保険金の支払い上限額は特定偶発事故より低めに設定される傾向にありますが、この補償があることで、費用倒れを心配せずに弁護士に依頼し、正当な権利を主張する道が開かれます。
契約によっては、特定の分野(離婚など)は対象外とする商品もあるため、加入前に補償範囲をよく確認することが重要です。
個人向け弁護士保険の保険金支払い事例10選
実務で想定されるリアルな事例を一つひとつ丁寧に解説します。保険がどのように役立つのか、具体的なイメージを掴んでいただければ幸いです。
【遺産相続】兄弟間の遺産分割協議が紛糾したケース
Aさんの父親が亡くなり、遺産である実家の土地建物の分割方法を巡って兄と対立しました。兄は「長男である自分がすべて相続すべきだ」と主張し、話し合いに応じません。
Aさんは法定相続分を主張したいものの、身内との争いに精神的に疲弊し、どうすればよいか分からずにいました。そこで弁護士保険を使い、相続問題に詳しい弁護士に相談。弁護士は、まずAさんの代理人として、法的な根拠に基づいた遺産分割案を兄側に提示しました。感情的な対立を避け、冷静な交渉を進めた結果、家庭裁判所での調停に移行。調停では、弁護士が不動産の適正な評価額を算出し、Aさんの権利を客観的な証拠と共に主張しました。
最終的に、不動産を売却してその代金を法定相続分に応じて分割する内容で調停が成立。Aさんは正当な権利を守ることができました。このケースでは、弁護士への相談料、調停手続きの着手金、そして解決時に支払う報酬金が保険から支払われ、Aさんの自己負担は大幅に軽減されました。
【離婚問題】夫の不貞行為に対する慰謝料と親権を請求したケース
B子さんは、夫の不貞行為が発覚したため離婚を決意しました。しかし、夫は不貞行為を認めず、慰謝料の支払いを拒否。さらに、「お前には経済力がない」と主張し、子どもの親権も渡さない構えでした。
当事者同士の話し合いでは埒が明かないと判断したB子さんは、弁護士保険を利用して離婚問題に強い弁護士に依頼しました。弁護士は、不貞行為を立証するための証拠(メールの履歴や写真など)を法的に有効な形で整理し、夫と交渉。確固たる証拠を前に夫も不貞行為を認めざるを得なくなり、慰謝料の支払いに応じました。
親権についても、弁護士がこれまでのB子さんの育児実績や今後の養育計画を具体的に主張し、家庭裁判所の調査官に説得力のある意見書を提出。
結果、B子さんが親権者となる形で、慰謝料と養育費の支払いを含む公正な条件での協議離婚が成立しました。保険からは、交渉から離婚協議書作成までの着手金や報酬金が支払われ、B子さんは経済的な不安なく、新たな一歩を踏み出すことができました。
【労働問題】会社から突然の「明日から来なくていい」不当解雇を言い渡されたケース
会社に長年勤めてきたCさんは、ある日突然上司に呼び出され、「業績不振のため」という曖昧な理由で即日解雇を言い渡されました。
解雇予告手当は支払われたものの、あまりに一方的な通告に納得がいきません。Cさんは弁護士保険を使い、労働問題専門の弁護士に相談しました。弁護士が詳しく聞き取ったところ、会社の業績は決して悪くなく、解雇には客観的で合理的な理由がないと判断。弁護士はCさんの代理人として会社と交渉し、今回の解雇が労働契約法に違反する「不当解雇」であり、無効である旨を内容証明郵便で通知しました。
会社側は当初、強硬な姿勢でしたが、弁護士が労働審判や訴訟も辞さない構えを見せると態度を軟化。最終的に、会社側が解決金を支払うことで合意退職する、という形で和解が成立しました。
Cさんは次の仕事を見つけるまでの生活資金を確保でき、精神的な区切りをつけることができました。保険からは、弁護士との法律相談料、会社との交渉や和解契約書作成にかかる着手金・報酬金が支払われました。
【近隣トラブル】隣家の深夜に及ぶ騒音に悩まされたケース
Dさん一家は、隣に引っ越してきた住人の深夜に及ぶ大音量の音楽や友人との騒ぎ声に悩まされていました。管理会社を通じて何度も注意してもらいましたが一向に改善されず、直接抗議すると逆上される始末で、Dさんは不眠に陥ってしまいました。
警察にも相談しましたが、民事不介入の原則から積極的な対応は望めません。そこでDさんは弁護士保険を使い、弁護士に介入を依頼。弁護士はまず、騒音の発生日時や音量を記録するようDさんに助言。その記録に基づき、受忍限度を超える騒音であることを法的に主張する内容証明郵便を隣人へ送付しました。
弁護士という専門家からの正式な通知に驚いた隣人は、ようやく事の重大さを認識。その後、弁護士を介して話し合いの場が持たれ、具体的な音量や時間帯に関するルールを定めた合意書を作成しました。
以降、騒音は劇的に改善され、Dさん一家は平穏な生活を取り戻しました。保険からは、相談料や内容証明郵便の作成費用、合意書作成に関する手数料などが支払われ、費用を気にせず専門的な対応を依頼することができました。
【ネットトラブル】SNSで事実無根の誹謗中傷をされたケース
高校生の息子を持つEさんは、息子がSNS上で同級生から「万引きの常習犯だ」といった事実無根の悪口を拡散されていることを知りました。投稿は瞬く間に広がり、息子は学校へ行けなくなるほど精神的に追い詰められてしまいました。Eさんは学校に相談しましたが、抜本的な解決には至りません。
そこで弁護士保険を使い、インターネットトラブルに詳しい弁護士に依頼。弁護士は、問題の投稿が名誉毀損にあたるとして、プロバイダに対し発信者情報開示請求の手続きを取りました。これにより投稿者を特定し、その親権者を相手に交渉を開始。弁護士が投稿の削除と、息子さんへの謝罪、そして精神的苦痛に対する慰謝料を請求した結果、相手方は要求に応じ、投稿はすべて削除されました。
息子さんの名誉は回復され、心のケアに専念できるようになりました。保険からは、発信者情報開示請求や相手方との交渉にかかった着手金、報酬金などが支払われ、複雑で専門的な手続きを安心して任せることができました。
【金銭トラブル】友人に貸したお金が返ってこないケース
Fさんは、友人が「事業で一時的に資金が必要」と言うので、借用書を交わした上で50万円を貸しました。しかし、返済期限を過ぎても一向に返済されず、連絡も次第に取りづらくなってしまいました。
友情を壊したくないという思いから強く催促できずにいましたが、このままでは泣き寝入りになってしまうと考え、弁護士保険を使って弁護士に相談しました。弁護士はFさんの代理人となり、まずは内容証明郵便で正式に返済を請求。それでも友人が応じなかったため、少額訴訟を提起しました。
裁判所への提出書類の作成や手続きはすべて弁護士が代行。裁判の場で、借用書という明確な証拠に基づきFさんの主張が認められ、友人に対して返済を命じる判決が下されました。
結果、Fさんは貸したお金を全額回収することができました。保険からは、相談料、内容証明郵便の作成費用、少額訴訟の着手金・報酬金が支払われ、友人との直接対決という精神的な負担を負うことなく、法的な手続きを通じて問題を解決できました。
【不動産トラブル】賃貸アパート退去時の高額な原状回復費用を請求されたケース
Gさんは、5年間住んだ賃貸アパートを退去する際、管理会社から「壁紙の全面張り替え」「フローリングの傷」などを理由に、敷金を大幅に超える20万円の原状回復費用を請求されました。
通常の使用による損耗(経年劣化)も含まれていると感じたGさんは納得できず、弁護士保険で弁護士に相談しました。弁護士は賃貸借契約書と国土交通省のガイドラインを精査し、Gさんが負担すべきなのは故意・過失による損傷部分のみであり、請求額の大部分は経年劣化にあたるため貸主が負担すべきだと判断。弁護士名で、請求の不当性を法的に指摘し、負担義務のある範囲を明確に算出した意見書を管理会社に送付しました。
専門家からの指摘を受け、管理会社は請求額を大幅に見直し。最終的に、Gさんが不注意でつけてしまった壁の穴の修繕費2万円のみを支払うことで合意に至りました。
保険からは、弁護士への相談料や交渉代理の費用が支払われ、不当な請求に対して泣き寝入りすることなく、少額の負担で問題を解決できました。
【交通事故】加害者側保険会社が提示する示談金が低すぎたケース
Hさんは、赤信号で停車中に後方から追突される交通事故に遭いました(過失割合0:100)。幸い怪我は軽傷でしたが、愛車には修理が必要な損傷を負いました。
しばらくして、加害者が加入する保険会社の担当者から示談金の提示がありましたが、その金額はHさんが想定していた修理費用や慰謝料より著しく低いものでした。Hさん自身で交渉を試みましたが、担当者は「これが弊社の基準です」の一点張りで話が進みません。
そこで、自身の自動車保険に弁護士費用特約が付いていなかったため、単独で加入していた弁護士保険を利用。交通事故に強い弁護士に交渉を依頼しました。弁護士は過去の判例や裁判基準(弁護士基準)を基に、適正な損害額を再計算。保険会社の担当者と直接交渉し、提示額の根拠の薄さを法的に追及しました。
その結果、当初の提示額から大幅に増額された、裁判基準に近い金額で示談が成立しました。保険からは弁護士への着手金・報酬金が支払われ、専門知識がない個人では難しい保険会社との交渉を、有利に進めることができました。
【学校問題】子どものいじめに対する学校側の対応が不十分だったケース
Iさんの子どもが、学校で複数の生徒から継続的に無視されたり、持ち物を隠されたりするいじめを受けていることが発覚しました。Iさんは何度も学校に相談し、対応を求めましたが、学校側は「子ども同士のいざこざ」として問題を矮小化し、具体的な調査や加害者への指導を行ってくれませんでした。
子どもの心身の不調が深刻化する中、Iさんは弁護士保険を使って弁護士に相談。弁護士は、いじめ防止対策推進法に基づき、学校が負うべき安全配慮義務について指摘。Iさんの代理人として校長と面談し、いじめの事実関係を時系列で整理した書面を提示の上、第三者委員会による調査や、加害者と被害者のクラス分離などの具体的な対応策を強く要求しました。
弁護士という法的な専門家が介入したことで、学校側の対応は一変。直ちに本格的な調査が開始され、加害生徒への指導と謝罪、再発防止策の策定が行われました。
保険からは、弁護士への相談料や学校との交渉代理費用が支払われ、個人では動かすことが難しかった学校組織に対して、迅速かつ適切な対応を促すことができました。
【痴漢冤罪】通勤電車内で痴漢と間違われ、警察に連行されたケース
※刑事事件は保険商品によって補償対象外の場合も多いため、注意が必要です。
会社員のJさんは、満員の通勤電車内で痴漢と間違われ、駅員に引き渡された後、警察署で事情聴取を受けることになりました。身に覚えのないJさんは容疑を否認しましたが、被害を訴える女性の証言もあり、状況は極めて不利でした。逮捕・勾留されれば、会社や家族に与える影響は計り知れません。
Jさんは、加入していた弁護士保険に「刑事事件の被疑者となった場合の弁護活動」が含まれていることを思い出し、すぐに保険会社へ連絡。紹介された刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼しました。弁護士は直ちに警察署へ駆けつけ、Jさんに黙秘権などの権利を説明し、不利益な供述調書が作成されないようサポート。
さらに、防犯カメラの映像や他の乗客の証言など、Jさんの無実を示す証拠を精力的に収集し、検察官に意見書を提出しました。弁護士の迅速かつ的確な活動の結果、嫌疑不十分としてJさんは不起訴処分となり、無事に釈放されました。
保険からは、弁護士への接見費用や着手金・報酬金が支払われ、人生を左右する危機的状況から早期に脱することができました。
事業者向け弁護士保険の保険金支払い事例10選
【債権回収】納品した商品の代金を取引先が支払ってくれないケース
中小企業を経営するK社は、取引先に総額100万円の商品を納品しましたが、支払期日を過ぎても入金がありませんでした。
経理担当者が何度も催促しましたが、「もう少し待ってほしい」と引き延ばされるばかりで、しまいには連絡が途絶えがちになりました。少額訴訟も考えましたが、手続きの手間や費用を考えると二の足を踏んでいました。
そこで、加入していた事業者向け弁護士保険を活用し、顧問弁護士に相談。弁護士はまず、K社の代理人として、法的措置も辞さない旨を明記した内容証明郵便を取引先へ送付しました。弁護士名での正式な請求に、相手方も事の重大さを認識し、すぐに連絡がありました。
弁護士が間に入って交渉した結果、一括での支払いは難しいものの、3回に分割して全額を支払うという内容の合意書を締結。無事に全額を回収することができました。
保険からは、弁護士への相談料、内容証明郵便の作成費用、交渉代理の着手金・報酬金が支払われ、貸し倒れのリスクを回避し、本業に支障をきたすことなく問題を解決できました。
【労務問題】解雇した元従業員から「不当解雇」で訴えられたケース
L社は、勤務態度に著しい問題があった従業員を、再三の指導・注意にもかかわらず改善が見られないため、やむなく普通解雇しました。
ところが後日、その元従業員から「解雇は不当だ」として、労働組合を通じて従業員としての地位確認と未払い賃金の支払いを求める団体交渉を申し入れられました。
L社は法的な手続きに則って解雇したつもりでしたが、対応に不安を感じ、弁護士保険を使って弁護士に依頼。弁護士は、これまでの指導記録や注意書の交付履歴などを精査し、解雇の正当性を法的に裏付ける証拠を整理しました。その上で団体交渉に同席し、L社の代理人として、解雇が客観的・合理的な理由に基づき、社会通念上相当なものであることを論理的に主張。
相手方の主張の矛盾点を突き、交渉を有利に進めました。最終的に、元従業員側が訴えを取り下げることで合意。訴訟に発展する前に問題を収束させることができました。保険からは、弁護士への相談料、団体交渉への同席費用、解決に至るまでの手数料などが支払われました。
【契約トラブル】業務委託先が納期を守らず、プロジェクトに損害が出たケース
IT企業であるM社は、システム開発の一部を外部の制作会社に委託しました。しかし、制作会社が約束の納期を大幅に過ぎてもシステムを完成させず、その結果、M社はクライアントへの納品が遅れ、契約に基づき違約金を支払う事態となりました。
M社は制作会社に対し、納期遅延によって生じた損害の賠償を求めましたが、相手方は「仕様が複雑だった」などと主張し、責任を認めません。M社は弁護士保険を使い、弁護士に代理交渉を依頼。弁護士は業務委託契約書を精査し、納期が明確に定められていること、そして相手方の帰責事由によって損害が発生したことを法的に証明。M社が被った損害額を具体的に算出し、制作会社に賠償を請求しました。
弁護士との交渉の結果、制作会社は責任を認め、M社がクライアントに支払った違約金相当額を支払うことで和解が成立しました。保険からは、弁護士への着手金・報酬金が支払われ、自社だけでは困難だった損害賠償請求を、専門家の力を借りて実現することができました。
【不動産トラブル】賃貸している店舗のテナントが家賃を滞納しているケース
不動産賃貸業を営むNさんは、所有するビルの一室を飲食店に貸していました。しかし、そのテナントが3ヶ月にわたり家賃を滞納。再三の督促にも応じず、連絡もつきにくい状況になってしまいました。
Nさんは契約を解除して退去してもらいたいと考えましたが、手続きが分からず、またトラブルになることを恐れていました。そこで弁護士保険を使い、不動産問題に強い弁護士に相談。弁護士は、まず内容証明郵便で契約解除の意思表示と物件の明け渡しを正式に通知しました。それでもテナントが応じなかったため、地方裁判所に建物明け渡し請求訴訟を提起。訴訟手続きはすべて弁護士が代行し、Nさんが出廷する必要はありませんでした。
裁判では、家賃滞納の事実と契約解除の正当性が認められ、Nさんの勝訴判決が下されました。その後、強制執行の手続きを経て、無事に物件の明け渡しが完了しました。保険からは、訴訟にかかった着手金、報酬金、実費などが支払われ、煩雑で精神的負担の大きい明け渡し請求をスムーズに進めることができました。
【知的財産権】競合他社に自社のウェブサイトのデザインを模倣されたケース
ECサイトを運営するO社は、多額の費用をかけて構築した自社サイトのデザインやキャッチコピーを、そっくりそのまま模倣した競合サイトを発見しました。これにより顧客が流出し、売上に大きな影響が出ていました。
O社は弁護士保険を利用し、知的財産権に詳しい弁護士に対応を依頼。弁護士は、O社のサイトが著作権法上の「著作物」にあたり、競合サイトの行為が著作権(複製権・翻案権)侵害にあたることを法的に検討。その上で、競合他社に対し、サイトの即時閉鎖と、侵害行為によってO社が被った損害の賠償を求める警告書を送付しました。
弁護士からの正式な警告を受け、競合他社は模倣の事実を認め、サイトを閉鎖。損害賠償についても交渉の結果、O社が納得する金額を支払うことで合意に至りました。保険からは、弁護士への相談料、警告書の作成・送付費用、交渉代理の着手金・報酬金などが支払われ、企業の生命線である知的財産を迅速に守ることができました。
【カスタマーハラスメント】顧客から執拗なクレームと土下座を要求されたケース
小売店を営むP社は、ある顧客から商品に対するクレームを受けました。初期対応に不備があったことは事実ですが、その後、その顧客は連日のように来店・電話をし、従業員に対して人格を否定するような暴言を浴びせたり、SNSでP社を誹謗中傷したり、さらには社長の土下座を要求するなど、その言動は常軌を逸していました。
従業員は恐怖を感じ、心身ともに疲弊。P社は、これは正当なクレームの範囲を超えた「カスタマーハラスメント」であると判断し、弁護士保険を使って弁護士に介入を求めました。弁護士はP社の代理人となり、その顧客に対し、今後の窓口をすべて弁護士に一本化するよう通知。これ以上の従業員への直接接触や誹謗中傷行為が続く場合は、威力業務妨害罪での刑事告訴や損害賠償請求などの法的措置を取ることを明確に伝えました。
弁護士が毅然とした対応を取ったことで、顧客からの過剰な要求は止み、従業員は安心して働ける環境を取り戻しました。保険からは、弁護士への相談料や通知書作成費用などが支払われました。
【風評被害対策】インターネット掲示板に根拠のない悪評を書き込まれたケース
飲食店を経営するQ社の店名が、匿名掲示板で「食中毒を隠蔽している」「従業員の態度が最悪」など、事実無根の悪評と共に書き込まれました。
その書き込みが原因で予約のキャンセルが相次ぎ、売上が激減。Q社は弁護士保険を利用し、ネットの風評被害対策に強い弁護士に相談しました。弁護士は、書き込みがQ社の社会的評価を著しく低下させる名誉毀損にあたるとして、掲示板の運営会社に対し、送信防止措置(削除)を依頼しました。運営会社が任意での削除に応じなかったため、裁判所に削除を命じる仮処分の申し立てを行いました。裁判所はQ社の主張を認め、迅速に削除命令を発令。
問題の書き込みは無事に削除され、さらなる被害の拡大を防ぐことができました。保険からは、相談料、サイト運営者との交渉費用、仮処分申し立てにかかる着手金・報酬金などが支払われ、専門知識がなければ対応が難しいネット上の風評被害に対して、迅速かつ効果的な対策を講じることができました。
【下請法違反】元請け企業から一方的な代金の減額を要求されたケース
ソフトウェア開発を行うR社は、元請け企業から受注したプロジェクトを納期内に完璧に納品しました。しかし、検収後、元請け企業は「軽微なバグがあった」「クライアントの評価が低かった」などと曖昧な理由をつけ、事前に合意していた代金から30%を一方的に減額すると通告してきました。
R社は、この要求が下請法に違反する不当な減額であると考えましたが、今後の取引への影響を懸念し、強く抗議できずにいました。そこで弁護士保険を使い、弁護士に相談。弁護士は、今回のケースが下請法第4条第1項第3号の「下請代金の減額の禁止」に明確に違反する可能性が高いと判断。R社に代わって元請け企業と交渉し、法的根拠を示して減額要求の撤回を求めました。
弁護士が中小企業庁への通報も視野に入れていることを伝えると、元請け企業は態度を改め、最終的に満額の代金を支払うことに応じました。保険からは弁護士への交渉代理費用が支払われ、立場の弱い下請け企業が泣き寝入りすることなく、正当な報酬を確保できました。
【情報漏洩】業務委託先のミスで顧客情報が流出してしまったケース
コンサルティング会社のS社は、顧客リストのデータ入力を外部の業者に委託していました。ところがある日、その委託先業者の従業員のミスにより、S社の顧客情報がインターネット上に流出する事故が発生。S社は直ちに顧客への謝罪と対応に追われ、会社の信用は大きく損なわれました。
S社は、委託先業者の契約不履行(善管注意義務違反)に基づき、損害賠償を請求したいと考え、弁護士保険を利用しました。弁護士は、S社が被った損害(顧客対応費用、信用回復のための広告費、逸失利益など)を具体的に算定。委託先業者との間で結ばれた業務委託契約書に基づき、相手方の責任を追及しました。交渉の結果、委託先業者が加入していた賠償責任保険を使い、S社が被った損害の大部分が補填される形で和解が成立しました。
S社の弁護士保険からは、自社側の代理人として活動した弁護士への着手金・報酬金が支払われ、複雑な損害額の算定や相手方との交渉を、専門家の支援を受けて適切に進めることができました。
【施設賠償】店舗内で顧客が転倒し、安全管理体制を問われたケース
スーパーマーケットを運営するT社は、雨の日に来店した顧客が、濡れた床で足を滑らせて転倒し、骨折する事故が発生しました。T社はすぐに救急車を呼び、見舞いにも行きましたが、後日、その顧客の代理人弁護士から「床の清掃を怠るなど、施設の安全管理に問題があった」として、治療費や慰謝料など高額な損害賠償を請求する内容証明郵便が届きました。
T社としては、滑りやすい旨の注意喚起やマットの設置など、対策は講じていたつもりでした。そこで弁護士保険を使い、弁護士に今後の対応を依頼。T社の弁護士は、事故当時の状況を従業員から詳しく聞き取り、防犯カメラの映像を確認。T社が講じていた安全対策を証拠として整理し、相手方弁護士と交渉しました。
その結果、T社にも一定の責任はあるものの、顧客側にも注意義務があったとして、請求額を大幅に減額した、妥当な金額で示談を成立させることができました。
保険からは、相手方との交渉代理にかかる着手金・報酬金が支払われ、訴訟に発展することなく、法的に適切な範囲で問題を解決できました。
弁護士保険に加入する10のメリットと副次的な効果
冒頭『弁護士保険の特徴とメリット|個人向け・事業者向けどちらにも共通する5つの項目』でご紹介したメリットとは少し視点を変え、ここでは弁護士保険に加入することで得られる「副次的・発展的なメリット」を7つ解説します。
時間的コストの大幅な削減と本業・本生活への集中
法的トラブルは、金銭だけでなく、解決までに膨大な「時間」を奪います。相手方との交渉、証拠の収集、書面の作成、裁判所への出廷など、すべてを自分で行うと、本来の仕事や生活が著しく圧迫されます。
弁護士に依頼すれば、これらの煩雑な手続きの大部分を代理人として一任できます。これにより、トラブル対応に費やすはずだった時間を、本来集中すべき業務や、家族と過ごす大切な時間にあてることが可能になります。
これは、機会損失を防ぐという意味で、目に見えない非常に大きな経済的メリットと言えます。
- 【個人向け】例えば、遺産分割協議で兄弟と延々と不毛な言い争いを続ける時間を、弁護士に任せて早期に終わらせ、自身の生活の立て直しに集中できます。
- 【事業者向け】悪質なクレーマー対応に経営者や従業員が費やす時間をなくし、そのリソースを新商品の開発や顧客サービス向上といった、企業の成長に直結する活動に振り向けることができます。
客観的視点に基づく最適な意思決定の支援
トラブルの渦中にいる当事者は、どうしても感情的になりがちです。「相手が許せない」という怒りや、「自分は悪くない」という思い込みが、冷静な判断を妨げ、かえって事態を悪化させてしまうことが少なくありません。
弁護士は、法律と過去の判例という客観的な物差しに基づき、状況を冷静に分析します。そして、感情論を排した上で、あなたにとって法的に最も有利な解決策(早期に和解すべきか、訴訟に踏み切るべきかなど)や、そのリスクを具体的に提示してくれます。
この専門家による客観的な助言が、最善の意思決定へと導いてくれるのです。
- 【個人向け】離婚問題において、感情的に親権を主張するだけでなく、弁護士の助言で経済面や今後の生活設計を冷静に考え、子どもの福祉にとって最善の選択肢を見出すことができます。
- 【事業者向け】取引先との紛争で、意地になって訴訟へ突き進む前に、弁護士が訴訟にかかる費用や時間、勝算を客観的に示してくれるため、事業への影響を最小限に抑える現実的な解決策(和解など)を選択しやすくなります。
精神的負担の軽減とメンタルヘルスの維持
法的トラブルがもたらすストレスは計り知れません。相手方からの理不尽な要求、先の見えない不安、孤独な戦いは、心身をすり減らし、不眠やうつ病などメンタルヘルスの不調を引き起こす原因にもなります。
弁護士に依頼するということは、この重圧を一人で抱え込まず、法律のプロフェッショナルと共有し、対応の矢面に立ってもらうことを意味します。
相手方との直接の接触を弁護士に一本化できるため、精神的な防波堤となり、心理的な負担が劇的に軽減されます。この心の平穏は、トラブルを乗り越える上で極めて重要です。
- 【個人向け】執拗なストーカー被害やDV問題など、身の危険を感じるような状況で、弁護士が代理人として間に入ることで、加害者と直接対峙する恐怖から解放されます。
- 【事業者向け】カスタマーハラスメントにおいて、従業員が直接矢面に立つ必要がなくなります。弁護士に対応を任せることで、従業員の精神的な安全を守り、離職を防ぐことにも繋がります。
第三者の介入による人間関係の維持・調整
特に親族間の相続問題や、友人との金銭トラブル、ご近所付き合いのもめ事など、感情的な対立が激化しやすい紛争においては、当事者同士で話し合うと、関係が修復不可能なほどこじれてしまうことが多々あります。
ここに弁護士という法的な権威を持つ中立的な第三者が介入することで、一旦冷静になるきっかけが生まれます。弁護士は感情ではなく「法的な権利義務」に基づいて交渉を進めるため、当事者間の直接的な衝突を避け、客観的な事実に基づいた話し合いの土壌を整えることができます。
結果として、必要以上に関係を悪化させることなく、現実的な落としどころを見つけやすくなります。
- 【個人向け】遺産分割で対立する兄弟の間に弁護士が入ることで、互いの主張を法的に整理し、感情的な罵り合いから、建設的な分割協議へと移行させ、完全な絶縁状態を回避できる可能性があります。
- 【事業者向け】長年の付き合いがある取引先との間で生じたトラブルでも、弁護士を介することで私情を挟まずに事務的に交渉を進められ、問題解決後に良好な取引関係を再構築できる可能性が残ります。
法的リテラシーの向上と将来リスクの自己管理能力の醸成
弁護士保険を活用して、気軽に専門家に相談する経験を重ねることは、自分自身の法的リテラシー(法的な知識や考え方)を自然と高めることに繋がります。
弁護士とのやり取りを通じて、「契約書ではこの点に注意すべきなのか」「こういう行為は法的にリスクがあるのか」といった実践的な知識が身につきます。
この経験は、単に目の前のトラブルを解決するだけでなく、将来、同様のトラブルを未然に防いだり、初期段階で自己判断できるようになったりするための、貴重な自己投資となります。
保険は、そのための「学びの機会」を経済的に提供してくれるツールとも言えるのです。
- 【個人向け】一度、賃貸物件の原状回復トラブルで弁護士に相談すれば、次回の引っ越しでは、入居時にどのような証拠写真を撮っておくべきかなど、自己防衛の知識が身につきます。
- 【事業者向け】労務問題で弁護士の助言を受ければ、就業規則の重要性や、従業員への指導における注意点を学び、より健全な労務管理体制を自社で構築していくことができます。
対外的な信用力の向上
特に事業者にとって、弁護士保険に加入している、あるいは顧問弁護士がいるという事実は、コンプライアンス(法令遵守)意識が高く、リスク管理が徹底されている企業であることの証左となります。
これは、金融機関からの融資審査や、大手企業との新規取引開始の場面において、企業の信用力を補強する一つのアピールポイントになり得ます。トラブル対応体制が整っているという安心感は、取引先や顧客、そして従業員からの信頼を高める効果も期待できます。
- 【個人向け】直接的な信用の向上という場面は少ないですが、例えばフリーランスとして活動する場合、プロフィールに「弁護士保険加入済」と記載することで、取引先に対して、契約や権利関係を疎かにしない、信頼できるビジネスパートナーであるという印象を与えることができます。
- 【事業者向け】ウェブサイトの会社概要などに「顧問弁護士」や「〇〇弁護士保険加入」と明記することで、しっかりとした経営基盤を持つ企業であることを対外的に示し、企業のブランドイメージや社会的信用の向上に繋がります。
弁護士を起点とした専門家ネットワークの活用
法的な問題は、必ずしも弁護士だけで完結するとは限りません。
例えば、相続問題では不動産の評価に不動産鑑定士が、税金の申告に税理士が必要です。また、事業においては、特許の出願に弁理士が、会社の登記変更に司法書士が必要になる場面があります。
弁護士は、こうした隣接する分野の専門家(税理士、司法書士、弁理士、行政書士、土地家屋調査士など)と幅広いネットワークを築いています。弁護士保険をきっかけに一人の信頼できる弁護士を見つけることができれば、その弁護士をハブとして、トラブルの内容に応じて最適な他の専門家をスムーズに紹介してもらえる可能性が広がります。
- 【個人向け】相続した不動産の売却を考えた際、遺産分割を担当した弁護士から、信頼できる司法書士や不動産業者を紹介してもらえる、といった展開が期待できます。
- 【事業者向け】新事業の立ち上げにあたり、ビジネスモデルの法務相談をした弁護士から、助成金の申請に詳しい社会保険労務士や、特許出願に強い弁理士を紹介してもらうなど、ワンストップで専門家の支援を受けやすくなります。
交渉における対等な立場を確保できる
トラブルの相手が、大企業や保険会社、あるいは専門の法務部を抱える組織である場合、知識や交渉力に圧倒的な差があり、個人や中小企業は不利な立場に立たされがちです。
相手方は法律のプロを立てて交渉してくるのに対し、こちらが素人では、知らず知らずのうちに不利な条件を飲まされてしまう可能性があります。
弁護士保険を使ってこちらも法律のプロである弁護士を代理人に立てることで、相手と対等な立場で交渉に臨むことができます。法的な知識と交渉の経験を背景に持つ弁護士が盾となり、また矛となることで、力関係の差を埋め、正当な権利を主張することが可能になるのです。
- 【個人向け】交通事故の示談交渉で、相手方の保険会社が提示する低い示談金に対し、弁護士が「裁判基準」で算定した正当な金額を主張・交渉してくれます。
- 【事業者向け】大手の取引先から一方的に不利な契約変更を求められた際も、弁護士が介入し、下請法や独占禁止法などの観点から対等な交渉を行い、自社の利益を守ります。
経営・生活の安定化に寄与する「お守り」としての機能
法的トラブルは、金銭的な損失だけでなく、解決までに多大な時間と精神的なエネルギーを消耗させ、本業や日常生活に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
いつ起こるとも知れない法的リスクに常に怯えるのではなく、「何かあっても弁護士にすぐ相談できる」という安心感は何物にも代えがたいものです。
この安心感は、日々の生活や事業活動において、精神的な安定をもたらす「お守り」のような機能を果たします。リスクを過度に恐れることなく、本来集中すべきこと、挑戦すべきことに専念できる環境を手に入れることができるのです。
- 【個人向け】予測不能な隣人トラブルや子どものいじめ問題などに対し、「いざという時の備えがある」と思えることで、日々の生活を安心して送ることができます。
- 【事業者向け】従業員との労務問題や顧客とのクレーム対応など、経営者が常に頭を悩ませるリスクに対し、専門家がバックにいるという安心感が、より積極的で健全な経営判断を後押しします。
潜在的なトラブルへの抑止力として働く
弁護士保険に加入しているという事実は、それ自体がトラブルを未然に防ぐ「抑止力」として機能する側面があります。
不当な要求をしてくる相手や、支払いを不当に遅らせようとする取引先に対して、「当方には顧問弁護士がおりますので、必要であれば相談します」あるいは「弁護士保険に加入しております」と伝えるだけで、相手の態度が軟化し、問題が解決に向かうケースは少なくありません。
これは、相手に「この人に無茶な要求をすると、法的な手段に訴えられ、かえって面倒なことになる」と認識させる効果があるためです。いわば、自らの権利を守るための「見えない盾」を持っている状態になり、理不尽な要求や攻撃を受けにくくなるのです。
- 【個人向け】悪質な訪問販売や、しつこい勧誘などに対し、「弁護士に相談します」の一言が、相手を退散させる有効な一撃になることがあります。
- 【事業者向け】モンスタークレーマーや取引先からの無理難題に対し、顧問弁護士の存在を匂わせることで、相手の過剰な要求を牽制し、従業員を不当なストレスから守ることにも繋がります。
弁護士保険のデメリットは何か?
弁護士保険にもデメリットや注意すべき点は存在します。加入を検討する上で知っておくべき5つのデメリットを解説します。
トラブルがなければ保険料が掛け捨てになる
弁護士保険は、病気やケガに備える医療保険などと同じく、利用する事態が発生しなければ支払った保険料は戻ってこない「掛け捨て」が基本です。法的トラブルは誰にでも起こりうるものですが、幸運にも長期間全くトラブルに遭わなければ、結果的に「保険料を払い続けただけ」ということになります。
月々の保険料は数千円程度でも、年間で見れば数万円の出費です。このコストを「安心のための必要経費」と捉えるか、「無駄な出費」と捉えるかは個人の価値観によります。
特に、生活環境が安定しており、トラブルに巻き込まれるリスクが極めて低いと感じる方にとっては、コストパフォーマンスが見合わないと感じる可能性があります。
「免責事由」に該当すると保険金が支払われない
保険に加入していても、すべての法的トラブルで保険金が支払われるわけではありません。保険契約には必ず「免責事由」という、保険金支払いの対象外となるケースが定められています。
代表的なものに、保険加入前にすでに発生していたトラブル(既発紛争)や、加入者が故意または重大な過失によって引き起こしたトラブル、犯罪行為や自然災害に起因する紛争などがあります。
また、保険商品によっては「離婚」や「相続」の一部が対象外であったり、事業者向け保険で「特許出願」に関する費用が対象外であったりします。
この免責事由をよく理解せずに加入すると、いざという時に「使えると思っていたのに使えない」という事態に陥る可能性があります。
補償には上限金額や不担保期間がある
弁護士保険の補償額は無制限ではありません。一つの事件あたりに支払われる保険金には「上限金額」が設定されています。例えば、法律相談料は合計10万円まで、着手金や報酬金は合計300万円まで、といった形です。大規模な訴訟に発展し、弁護士費用がこの上限を超えた場合、差額は自己負担となります。
また、加入後すぐに保険が使えない「不担保期間(待機期間)」が設けられていることが一般的です。これは、トラブル発生を予見してからの「駆け込み加入」を防ぐためです。
例えば、離婚や相続などの一般事件については「加入から1年間は対象外」といった定めがある場合、その期間内に発生したトラブルでは保険を利用できません。
弁護士が不要な軽微なトラブルでは活用しにくい
弁護士保険は、あくまで弁護士に相談・依頼する際の費用を補償するものです。そのため、弁護士を立てるまでもないごく軽微なトラブルでは、そのメリットを享受しにくいと言えます。
例えば、数千円程度の少額な金銭トラブルや、当事者同士の話し合いで十分に解決可能な問題の場合、わざわざ弁護士に依頼するケースは少ないでしょう。こうしたトラブルしか想定されないのであれば、毎月保険料を支払う必要性は低いかもしれません。
弁護士保険は、自分一人では解決が難しい、あるいは法的な専門知識が必要となる、ある程度複雑な事案に直面したときにこそ、真価を発揮するものです。
弁護士や保険会社の対応に不満が残る可能性
保険を使えば必ず満足のいく結果が得られるとは限りません。保険会社から紹介された弁護士と相性が合わなかったり、その弁護士の対応や方針に納得できなかったりする可能性はゼロではありません。
また、保険金の請求手続きにおいて、トラブルの状況を保険会社に詳細に説明する必要がありますが、その審査の過程で「今回のケースは補償対象外です」と判断されることもあり得ます。
期待していたサポートが得られなかった場合、保険料を支払ってきた意味が問われることになり、結果として不満だけが残ってしまうリスクも考慮しておく必要があります。
弁護士保険への加入条件として設けられている主な項目
弁護士保険の加入条件は、個人向けと事業者向けで若干異なりますが、基本的には「将来の予測できないリスクに備える」という保険の原則に基づいています。以下にそれぞれの主な条件を解説します。
【個人向け】加入条件
個人向けプランに加入するための主な条件は、加入者個人の状況に関するものです。
① 日本国内に居住していること
ほとんどの弁護士保険は、日本の法律や司法制度を前提として設計されているため、保険契約者および主な被保険者(補償の対象となる人)が日本国内に居住していることが基本的な条件となります。
海外で発生したトラブルや、海外在住の方を対象とした補償は、原則として範囲外となることが一般的です。保険は国内の法制度下で発生するリスクを想定しているため、この地理的な条件は必須とされています。
② 反社会的勢力に該当しないこと
これは、すべての保険契約に共通する極めて重要な条件です。保険契約者や被保険者が、暴力団、暴力団員、その他の反社会的勢力に該当しないことが求められます。
保険という公的な性格を持つ制度が、犯罪組織の活動資金源となることを防ぐための社会的な要請に基づくものです。加入時の告知だけでなく、加入後にこれらの勢力と関係があることが判明した場合には、契約が解除されることになります。
③ 加入時点で具体的な法的トラブルを抱えていないこと
弁護士保険は、将来発生するかもしれない不測の法的トラブルに備えるためのものです。そのため、保険の申し込み時点ですでに発生しているトラブル(既発紛争)や、発生することが具体的に予測されているトラブルについては、補償の対象外となります。
例えば、すでに相手方から内容証明郵便が届いている、裁判所から訴状が届いている、といった状況では加入してもその件については保険を使えません。保険の公平性を保つための重要な原則です。
【事業者向け】加入条件
事業者向けプランでは、個人向けの条件に加え、事業体そのものに関する条件が問われます。
① 日本国内に本店または主たる事務所があること
個人向けと同様に、事業活動の基盤が日本国内にあることが前提となります。日本国内で法人登記されている法人、または日本国内に主たる事務所を置く個人事業主が対象です。
日本の会社法や労働法、各種業法など、国内の法的環境下で事業を営む中で発生するリスクを補償の対象としているため、この条件が設けられています。海外の現地法人や支店でのトラブルは、原則として対象外です。
② 反社会的勢力と関係のない事業体であること
個人向けの条件と同様に、事業者においてもコンプライアンスの観点から極めて厳しく審査されます。法人そのもの、役員、主要な株主などが反社会的勢力と一切関係がないことが絶対条件です。
もし関係があることが判明すれば、契約は即時解除されます。これは、企業の社会的責任と、保険制度の健全性を維持するために不可欠な項目です。
③ 加入時点で具体的な法的紛争を抱えていないこと
個人向けの「既発紛争の不担保」と同じ原則です。申し込み時点ですでに発生している取引先との訴訟、従業員との労働審判、行政からの指導や調査など、具体的な法的紛争案件を抱えている場合、その案件を目的として保険に加入することはできません。
保険はあくまで将来のリスク管理ツールであり、すでに燃え始めている火事を消すためのものではない、という考え方に基づいています。
④ 一部の特定の業種ではないこと
多くの保険ではほとんどの業種をカバーしていますが、一部の保険商品では、その事業内容から法的なトラブルの発生頻度が極めて高いと想定される特定の業種について、加入を制限したり、特別な条件下での引き受けとなったりする場合があります。
例えば、風俗関連業、一部の金融業、探偵業などがこれに該当することがあります。加入を検討する際は、自社の業種が引き受けの対象となっているかを確認する必要があります。
弁護士保険の補償対象者
弁護士保険は一般的に18歳以上でなければ加入できませんが、保険契約者が加入条件を満たしていれば、被保険者が条件を満たしていない場合でも保険が適用される場合があります。
例えば、自身(40歳)が弁護士保険に加入していて、18歳未満の自分の子供がいじめ被害に遭い、加害者の親や学校側とトラブルになった際にも保険を利用することができる場合もあります。
しかし、保険会社によって補償対象者は異なるため、加入前に確認をしておきましょう。
待機期間と不担保期間を知っておこう
弁護士保険には、待機期間と不担保期間が設けられているため、加入後すぐ保険が適用されるというわけではありません。
弁護士保険に加入する前に、待機期間と不担保期間がどれくらいかを確認しておきましょう。
待機期間について
待機期間とは、契約日から一定期間(3か月程度)、保険金が受け取れない期間のことです。
基本的に待機期間中は、法的トラブルが生じたとしても保険は適用されません。
ただし、交通事故などの偶発事故(急激かつ偶然かつ外来の事故)の場合は、通常待機期間が適用されずに保険金を受け取ることができます。
待機期間が適用されるかどうかを判断することが難しいケースもありますので、待機期間中に問題が発生した場合は、保険適用の有無を保険会社に問い合わせてみましょう。
不担保期間について
不担保期間とは、待機期間とは別に設けられている特定の法律トラブルに関して保険金が受け取れない期間のことです。
不担保期間が適用される主な法律トラブルには、相続や親族間トラブル、離婚トラブル、労働問題、ストーカー被害などがあります。
不担保期間は1年程度としている保険会社が多いですが、保険会社によって少し異なりますので、加入前に確認しておきましょう。
主要な弁護士保険会社を比較
弁護士保険の保険料や保険金額、支払上限などはそれぞれの保険会社で異なります。
ここでは代表的な弁護士保険を3種類ピックアップして比較します。
弁護士費用保険ミカタ

【公式サイト】http://m01.preventsi.co.jp/
| 運営会社 | ミカタ少額短期保険 |
|---|---|
| 商品名 | 弁護士費用保険ミカタ |
| 保険料 | 月額2,980円 |
| 補償範囲 | 特定偶発事故 一般事件 |
| 待機期間と不担保期間 | 一般事件:3か月 離婚:1年 相続:1年 リスク取引:1年 親族:1年 |
| 補償限度額(一般事件) | 200万円 |
| 補償限度額(偶発事故) | 300万円 |
| 補償限度額(通算) | 1,000万円 |
| 免責金額 | 5万円 |
| 公式ホームページ | https://mikata-ins.co.jp/ |
「弁護士費用保険ミカタ」は、日本弁護士連合会(日弁連)と協定を結んでいる弁護士保険です。
日弁連との提携で実現した弁護士直通ダイヤルは、1回15分だけですが、弁護士に電話で無料相談ができるというサービスです。
また、日弁連を通じて各地域の弁護士を無料で紹介してもらえる弁護士紹介サービスや、弁護士へ無料相談できるアプリの弁護士トークも用意されています。
補償対象は契約者本人だけですが、1人につき月額1,500円支払って「家族特約(家族のミカタ)」を利用することで、3親等内の家族も契約者本人と同等の補償を受けることができます。
弁護士費用保険ミカタは、弁護士に気軽に相談したい、弁護士を探す手間を省きたいといった方におすすめの弁護士保険といえるでしょう。
弁護士費用保険コモン+

【公式サイト】https://yell-lpi.co.jp/
| 運営会社 | エール少額短期保険 |
|---|---|
| 商品名 | 弁護士保険コモン+ |
| 保険料 | ライト+:月額1,080円 レギュラー+:月額2,480円 ステイタス+:月額4,980円 |
| 補償範囲 | 特定偶発事故 一般事件 |
| 待機期間と不担保期間 | 一般事件:3か月 離婚:3年 相続:2年 親族:1年 |
| 補償限度額(一般事件) | ライト+:30万円 レギュラー+:100万円 ステイタス+:300万円 |
| 補償限度額(偶発事故) | ライト+:30万円 レギュラー+:100万円 ステイタス+:300万円 |
| 補償限度額(通算) | ライト+:360万円 レギュラー+:1,200万円 ステイタス+:3,600万円 |
| 免責金額 | 1回目:5万円 2回目:10万円 |
| 公式ホームページ | https://yell-lpi.co.jp/ |
「弁護士費用保険コモン+」は、ライト+、レギュラー+、ステイタス+の3つから好きなプランを選べる弁護士保険です。
プランごとに補償限度額が変わるので、どれだけ補償を受けたいかというニーズに合わせて選択できます。
補償対象は、契約者本人と18歳未満の子どもです。
また「ファミリー特約」を付帯することで配偶者1名と30歳未満の未婚の子ども(5人まで)も補償対象にできます。
こちらも『弁護士直通ダイヤルや弁護士検索サポートを利用できるので、自分に合ったプランを選びたい、弁護士に気軽に相談したいといった方におすすめと言えます。
弁護士保険の加入がおすすめの方
弁護士保険がおすすめなのは、以下のような方です。
収入・経済面の懸念があり、弁護士費用を支払えない方
弁護士に相談・依頼する際の費用捻出が難しい方は、弁護士保険への加入がおすすめです。
弁護士保険で費用が補償されれば、弁護士に依頼できずに泣き寝入りすることを防げます。
公共交通機関で長時間の通学・通勤をする方
バスや電車などの公共交通機関をよく利用する方は、混み合った車内で痴漢冤罪などのトラブルに遭遇する可能性があります。
「弁護士費用保険コモン+」の痴漢冤罪ヘルプコールなどを利用すれば、万が一痴漢冤罪に巻き込まれても初動に必要な弁護士費用の補償が受けられます。
小・中・高生の子どもを持つ保護者の方
学校生活で子どもがいじめに遭う、部活で大怪我をするなどのトラブルがあった場合、学校や加害者側が問題を認めないといったケースも考えられます。
弁護士保険に加入していることで、弁護士に依頼しやすくなり、それによって学校や加害者側の法的責任を追求しやすくなります。
外出する機会が多い方
外出する機会が多いと、自動車事故や自転車事故などに巻き込まれる可能性があり、車を運転する場合は人身事故や物損事故を起こす可能性もあり得ます。
自動車事故や自転車事故は偶発事故に当てはまるので、基本的には弁護士保険に加入してからすぐに補償を受けられます。
弁護士保険に関するよくある質問
最後に弁護士保険に関するよくある質問に回答します。
Q1.弁護士保険は入っておいたほうが良いのでしょうか?
弁護士保険では、法律問題に遭ったときの弁護士費用が補償されます。
現代の法律問題は、親族問題や離婚問題、相続問題、近隣問題、労働問題・ハラスメント、医療過誤、インターネット被害、子どものいじめ、消費者トラブルなど多岐にわたります。
このような万が一のトラブルに備えておきたいという場合には、弁護士保険に加入することをおすすめします。
Q2.弁護士保険と同じような保険はありますか?
例えば、自動車保険に付帯できる弁護士特約があります。
ただし、自動車保険の弁護士特約の補償は原則、もらい事故などで相手方に損害賠償請求をおこなう場合に備える補償です。
そのため、以下のようなケースでは補償されない可能性が高いです。
- 自動車に関する事故ではない場合
- ご自身に故意又は重大な過失があり損害賠償を支払う必要がある場合
このようなことへ備える場合は、弁護士特約ではなく、弁護士保険への加入をおすすめします。
Q3.弁護士保険を途中解約した場合、保険料は戻ってきますか?
弁護士保険は一般的に掛け捨てなので、途中解約した場合でも支払った保険料が戻ってくることはありません。
Q4.自分で選んだ弁護士でも補償対象になるのですか?
保険会社や保険商品にもよりますが、保険会社が提携している弁護士以外でも補償対象になる場合があります。
Q5.すでに起こっている問題の弁護士費用を節約することは可能ですか?
先に述べたように、契約前に起こったトラブルの弁護士費用は、弁護士保険では補償できません。
さいごに
弁護士保険は、弁護士への相談費用を一部または全部補償してくれる保険です。
「弁護士費用保険ミカタ」など、各種特約や付帯サービスを利用できる弁護士保険もあります。
法的問題を抱える可能性は誰にでもあるので、万が一の場合に泣き寝入りしたくない、家族を法的問題から守りたいといった方は、弁護士保険への加入を検討してみてはいかがでしょうか。
KL2020・OD・039