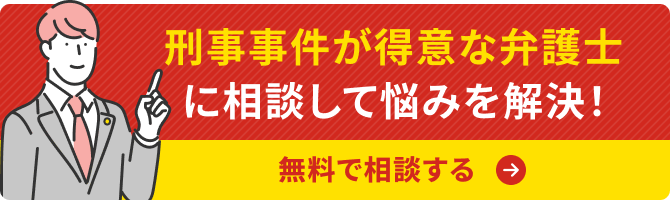令和5年(2023年)のひき逃げの検挙率は72.1%となっています(令和6年犯罪白書)。
一般的な刑法犯の検挙率は38.3%であるため(令和6年犯罪白書)、ひき逃げの検挙率は非常に高いといえます。
本記事では、ひき逃げ事件の検挙率、加害者が負う責任、逮捕後の流れについてわかりやすく解説します。
さらに、早期に自首することの重要性や弁護士に相談するメリットなど、ひき逃げ事件を起こした際にどう対応すべきかの指針についても説明します。
ひき逃げの検挙率はどのくらい?死亡事故であれば100%?
ひき逃げ事件の検挙率は年々変動がありますが、全体として高い水準にあります。
以下は、警察庁交通局の統計をグラフと表にしたものです。
引用元:令和6年犯罪白書
年次(和暦) 年次(西暦) 発生件数 発生件数_
死亡事故発生件数_
重傷事故発生件数_
軽傷事故検挙件数 検挙件数_
死亡事故検挙件数_
重傷事故全検挙率 死亡事故検挙率 重傷事故検挙率 令和元年 2019年 7,491件 127件 688件 6,676件 4,823件 128件 579件 64.4% 100.8% 84.2% 令和2年 2020年 6,830件 93件 730件 6,007件 4,798件 91件 583件 70.2% 97.8% 79.9% 令和3年 2021年 6,922件 91件 669件 6,162件 4,963件 90件 581件 71.7% 98.9% 86.8% 令和4年 2022年 6,980件 99件 681件 6,200件 4,837件 100件 541件 69.3% 101.0% 79.4% 令和5年 2023年 7,183件 84件 755件 6,344件 5,177件 86件 664件 72.1% 102.4% 87.9% 引用元:令和6年犯罪白書
統計によれば、令和5年(2023年)中に発生したひき逃げの全検挙率は72.1%でした。
特に被害者が死亡した事故の場合、検挙率はほぼ100%と非常に高く、重傷事故の場合でも例年80%前後が検挙されています。
一部、検挙率が100%を超えている年がありますが、これは前年の事件の犯人が捕まったケースも含めているためです。
このようなデータを踏まえると、死亡事故や重傷事故においては、ひき逃げで犯人が逃れられることはまずないといえるでしょう。
一方、「軽いけがなら逃げ切れるのか」といわれるとそうではありません。
近年では、防犯カメラの技術進歩によってより鮮明な映像が残っているほか、ドライブレコーダーが普及したことによって、逃走車両のナンバーや車種が割り出され、犯人の確保につながるケースが増えています。
たとえ一時現場から逃げても、警察は科学的な捜査手法で追跡し、いずれ犯人に辿り着く可能性が高いでしょう。
ひき逃げ加害者が負う責任と科せられる主な罰則
ひき逃げ事故を起こした場合、加害者は刑事・行政・民事の3つの責任を負うことになります。
それぞれ具体的にどのような処罰やペナルティが科せられるのか、順に見ていきましょう。
刑事責任|拘禁刑や罰金などの刑罰を受ける可能性がある
まず刑事面では、ひき逃げ加害者には複数の犯罪が成立すると考えられます。
日本の法律には「ひき逃げ罪」という単独の罪名はありませんが、ひき逃げ行為は以下3つの犯罪が同時におこなわれたものと整理できます。
- 過失運転致死傷罪
- 報告義務違反
- 救護義務違反
それぞれの犯罪の概要や刑罰について、詳しく見ていきましょう。
過失運転致死傷罪|運転時の過失により相手を死傷させた場合の罪
過失運転致死傷罪は、自動車の運転における注意義務違反によって、他人を死傷させた場合に成立する犯罪です。
たとえば、信号無視や前方不注意、スピードの出しすぎなど、故意ではなくても結果的に事故を引き起こし、人を傷つけた場合などが挙げられます
刑罰は「7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」(自動車運転死傷処罰法第5条)とされていますが、判決で認められる量刑は被害者の死傷の程度や被害弁償の有無、加害者の態度等の具体的事情によってさまざまです。
報告義務違反|交通事故後に警察へ報告しなかった場合の罪
報告義務違反は、交通事故を起こしたにもかかわらず、警察へ報告をしなかった場合に成立する犯罪です。
法定刑は「3ヵ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金」(道路交通法第119条第1項第17号)となっています。
なお、報告義務違反をしている場合、捜査機関に「逃亡するおそれがある」と判断されやすくなるため、逮捕などの身柄拘束をされる可能性が高まります。
救護義務違反|被害者を救護せず立ち去った場合の罪
救護義務違反は、交通事故を起こした際に被害者の救護をおこなわず、その場から立ち去った場合に成立する犯罪です。
被害者の死傷が当該運転者の運転に起因する場合の救護義務違反の法定刑は「10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」(道路交通法第117条第2項)となっており、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪と併せて処罰されることが一般的です。
行政処分|被害者の状況に関わらず、一発で免許取り消しに
ひき逃げをした場合は、刑事罰とは別に厳しい行政処分が下されます。
まず、救護義務違反は道路交通法の違反点数制度において35点が付加される重大違反です。
なお、報告義務違反があった場合はこれに吸収されます。
さらに、被害の状況と加害者の責任に応じて、以下のように違反点数が加算されます。
交通事故の種別 交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合における点数 左の欄に指定する場合以外の場合における点数 人の死亡に係る事故 20点 13点 傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が3月以上又は後遺障害が存するもの 13点 9点 傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が30日以上3月未満であるもの 9点 6点 傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が15日以上30日未満であるもの 6点 4点 傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が15日未満であるもの又は建造物の損壊に係る交通事故 3点 2点 引用元:交通事故の付加点数 警視庁
たとえば、加害者が一方的に交通事故を起こして被害者を死亡させてしまった場合、救護義務違反35点に加えて、死亡事故の違反点数20点が付加されて「55点」になります。
救護義務違反は「特定違反行為」という区分に該当するため、違反点数が55点の場合は欠格期間は7年間となる可能性が高いでしょう。
【参考】行政処分基準点数 警視庁
民事責任|被害者に対して損害賠償責任を負う
ひき逃げ事故を起こした加害者は、被害者に対して民事上の損害賠償責任も負います。
具体的には、被害者の治療費、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害が残ればその逸失利益・慰謝料などの賠償を請求されるでしょう。
通常、加害者が自動車保険に入っていれば、保険会社から被害者に対して補償がおこなわれます。
しかし、ひき逃げ事件では保険会社に対しても交通事故の発生を通知していないケースが多いです。
通知をしていない場合、通知義務を怠ったことにより拡大した損害については保険金が支払われず、一部の賠償金を自己負担することになる場合があります。
ひき逃げ事件を起こして逮捕・刑事裁判に至るまでのおおまかな流れ
ここでは、ひき逃げ事件を起こしたあとの刑事手続きの流れについて解説します。
1.警察が事情聴取や現場検証などの捜査を開始する
ひき逃げ事件では、被害者や目撃者からの通報によって警察が事故を認知し、捜査を開始するのが通常です。
警察は、被害者や目撃者などの証言、防犯カメラ映像、ナンバープレートの目撃情報やドライブレコーダー映像、現場に落ちた破片、付着した塗料などあらゆる手がかりをもとに犯人追跡を進め、逃走車両および運転者の特定を急ぎます。
2.警察から呼び出しを受けたり、自宅を訪問されたりして逮捕に至る
犯人が判明すると、警察は任意の事情聴取を求めるか、逮捕状を請求して通常逮捕に踏み切ります。
【通常逮捕の主な要件】
- 犯罪をしたという相当な理由(疑い)がある
- 証拠隠滅や逃亡のおそれがある
ひき逃げの場合は「現場から立ち去った」という事実があるため、逃亡のおそれが高いと判断される傾向があります。
もし逮捕された場合は「身柄事件」として次項以降の流れに従って手続きが進むことになるでしょう。
3.【逮捕後48時間以内】警察から取調べを受け、検察へ送致される
逮捕後は、警察署の留置場に留め置かれ、まず警察官による取調べを受けます。
ここではひき逃げの経緯や事故の詳細について確認され、供述調書が作成されます。
そして、逮捕から48時間以内に事件と身柄が検察官へと送致されることになります。
4.【送致後24時間以内】検察官が被疑者を勾留するか否か判断する
検察官は送致を受けたあと24時間以内に、被疑者を勾留するかどうか判断します。
【勾留の主な要件】
- 犯罪をしたという相当な理由(疑い)がある
- 住居不定または逃亡・証拠隠滅のおそれがある
ひき逃げは捜査に時間を要する傾向があり、特に被害が大きい場合には勾留請求がおこなわれやすいです。
裁判所に対して勾留請求をおこなわれて、裁判官が勾留決定をした場合は、引き続き身柄を拘束されます。
5.【勾留後最長20日以内】身柄拘束が継続し、検察官が起訴するかの判断をする
勾留が決定すると、まず原則10日間の拘束となり、捜査の必要に応じてさらに最長10日間延長されます。
勾留中は警察・検察による捜査がおこなわれ、被疑者は引き続き留置場での生活を強いられるでしょう。
そして検察官は、勾留期間中に集めた証拠や被疑者の供述内容を精査し、起訴するか不起訴処分とするかを判断します。
起訴猶予とする場合や、勾留期間中に判断をすることができなかった場合は、ここで釈放となります。
ひき逃げ事件では起訴される可能性が高いですが、被害者と示談が成立していれば不起訴となるケースもないわけではありません。
6.刑事裁判が開始され有罪・無罪が確定する
検察官が起訴を決めると、公判請求されて刑事裁判が開かれます。
裁判では、事故状況や逃走経緯、動機、反省の態度、被害者との示談状況などひき逃げに関するあらゆる事情が審理され、裁判官が最終的な判決を言い渡します。
判決内容に不服がなければ判決が確定し、実刑ならば刑務所へ収容、執行猶予付き判決または無罪判決ならば釈放となります。
ひき逃げをしたときは速やかに自首すべき
ひき逃げをした場合は、できるだけ早く警察に自首することが望ましいです。
逃げ続けたとしても、前述のとおり検挙される可能性は高いですし、警察・検察は「逃げるつもりだ」「証拠を隠すつもりだ」と疑いを強めることになります。
反対に、人身事故後に早い段階で自首をすることで、捜査機関に身柄を拘束されない「在宅事件」になる可能性が高まります。
さらに刑法第42条1項には「捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と定められているため、たとえ刑事裁判で有罪判決を下されたとしても、自首をしなかった場合と比べて刑罰が軽くなる可能性があります。
もちろん、減軽は裁判所の判断によるため、必ず刑が軽くなるわけではありませんが、自首する場合としない場合で法律上取り扱いが異なることは知っておくべきでしょう。
刑事事件が得意な弁護士に相談・依頼することもおすすめ
ひき逃げ事件を起こした場合、刑事事件が得意な弁護士に依頼することをおすすめします。
【ひき逃げ事件を弁護士に依頼するメリット】
- 取調べに関するアドバイスが受けられる
- 自首・出頭の際に弁護士が同行してくれる
- 身柄拘束が必要ない旨の働きかけをしてくれる
- 被害者の連絡先を手に入れて示談交渉をしてくれる など
弁護士に依頼しサポートを受けることで、身柄拘束を回避したり、不起訴処分を獲得できたりする可能性が高まります。
初回無料相談や土日祝日相談などに応じている弁護士もいるため、ベンナビ刑事事件で近くの弁護士を探して、相談することをおすすめします。
ひき逃げ事件についてよくある質問
最後に、ひき逃げ事件に関するよくある質問に回答します。
ひき逃げに気付かなかった場合はどうなるのか?
ひき逃げは「人身事故を起こしたと認識していながら逃走した場合」に成立する犯罪です。
そのため、自分では人身事故を起こしたことをまったく気付かずに現場を立ち去っていた場合は、救護義務違反・報告義務違反は成立しないことになります。
ただし「気付かなかった」という主張が認められるケースは限定的であり(例:夜間の小動物との接触と誤認した場合等)、防犯カメラの映像などから「気付かないはずがない」と判断される可能性は十分ありえます。
なお、救護義務違反・報告義務違反が成立しなかったとしても、人身事故を起こしている以上は過失運転致死傷罪に問われることになるでしょう。
被害者に「大丈夫」と言われて立ち去った場合でもひき逃げになる?
事故当時、被害者本人がその場で「平気です」「警察はいらない」と言った場合でも、運転者の義務が免除されるわけではありません。
あとになって被害者が痛みを訴えて病院に行き、診断書を警察に提出すれば、人身事故として扱われ、救護義務違反・報告義務違反が成立する可能性が高くなります。
被害者が子どもや高齢者だと、パニックや遠慮から「大丈夫」と言ってしまうことが多いですが、相手の言葉を鵜呑みにせず必ず警察に通報し、病院への受診を促しましょう。
ひき逃げは初犯でも実刑になる?
ケースによりますが、初犯であっても実刑判決となる可能性は十分あります。
特に、被害者の死亡・重傷といった重大事故の場合や、飲酒運転・無免許運転でのひき逃げなど悪質性が高い場合は、初犯であっても厳しい判決が下される可能性があります。
一方、被害者が軽傷であり、被害者に対して十分謝罪し示談を成立させている場合は、起訴猶予や執行猶予付き判決となる可能性があるでしょう。
さいごに|ひき逃げをしてしまいどうすればいいかわからないときは弁護士に相談を!
ひき逃げ事件の検挙率は72.1%であり、死亡事故に限ればほとんど100%に近い割合です。
そのため「高い確率で捜査機関に検挙される」ということを理解しておきましょう。
もしひき逃げ事件を起こした場合は、できる限り早く弁護士に相談することが望ましいです。
弁護士に相談・依頼することで、自首に同行してもらえたり、被害者との示談交渉を任せられたりします。
まずは「ベンナビ刑事事件」で近くの刑事事件が得意な弁護士を探して、ひき逃げ事件について相談し、サポートを受けることをおすすめします。