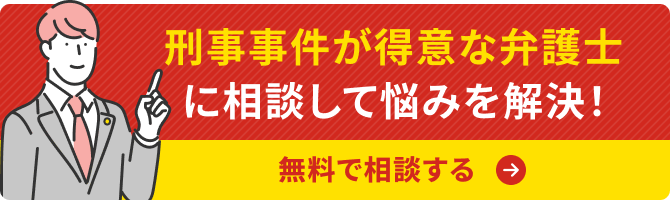現在、本罪で警察の捜査を受けている方の中には、「余罪があることを知られたらどうなるのか」「捜査はどこまで及ぶのか」と不安に感じている方もいるのではないでしょうか。
特に初めての逮捕や取り調べに直面すると、自分の身に何が起きるのか想像もつかず、不安が一層強まるものです。
この記事では、「余罪捜査がどこまでおこなわれるのか」というテーマについて、余罪の定義、発覚のきっかけ、罪の重さへの影響など、気になるポイントを網羅的に解説します。
また、「余罪を自白するべきか?」といった悩みへの対応方針や、弁護士に相談することで得られるメリットも紹介します。
今後の対応を冷静に考えるためにも、正しい知識を身につけましょう。
余罪捜査はどこまでおこなわれる?
警察に逮捕・勾留されている最中、「ほかにも何かやっていないのか?」と尋ねられた経験がある方もいるかもしれません。
ここでは、余罪捜査の基本的なルールと、実際にどのようなケースで余罪まで調べられるのかを解説します。
そもそも余罪とは?わかりやすく言うと捜査中の犯罪(本罪)以外の罪
「余罪」とは、現在捜査の対象になっている犯罪(本罪)とは別に、被疑者が関与したとされる未解決の犯罪のことです。
刑事手続では、「本罪」が起訴状や逮捕状に記載された特定の犯罪事実であるのに対し、「余罪」はその記載には含まれていない行為を指します。
たとえば、万引きで逮捕された人が「実はほかの店でも同じことをしていた」とすれば、それは別の犯罪行為として、余罪に該当する可能性があります。
一部の例外を除き、原則として余罪は調べない
刑事手続には「事件単位の原則」が適用されます。
これは、逮捕・勾留・起訴・裁判といった刑事手続の効力は、あくまで逮捕状、勾留状、起訴状に記載された被疑事実や公訴事実に限られるという考え方です。
そのため、現在拘束されている容疑(本罪)とは無関係な余罪について、警察が取り調べをおこなうことは原則として認められていません。
余罪を追及するには、別途その犯罪についての逮捕状や捜索差押許可状を取得する必要があります。
常習性が疑われる犯罪は、徹底的に本罪の捜査がおこなわれた結果余罪が発覚する場合がある
余罪捜査には「事件単位の原則」が適用されますが、本罪の捜査の過程で余罪が発覚することがあります。
とくに「常習性」が認められる犯罪では、警察は余罪まで徹底的に捜査する傾向があります。
たとえば、次のような犯罪では、余罪が発覚しやすいでしょう。
- 盗撮やのぞき、痴漢などの性犯罪
- 万引きなどの窃盗事件
- 詐欺や特殊詐欺
- 薬物の使用や所持
これらは、一度の犯行ではなく、過去にも複数回にわたって繰り返されている傾向が高いためです。
警察は、本罪の逮捕後に押収したスマートフォンやパソコン、防犯カメラ映像、物的証拠などをもとに、過去の犯行とのつながりを探ります。
盗撮事件ではスマートフォン内の画像データから、薬物事件では過去の通信履歴から取引状況が判明するケースもあります。
そのほか、余罪取り調べが任意捜査として例外的におこなわれる主なケース
例外的に余罪の取調べがおこなわれるケースも存在します。
たとえば、同種の犯罪が複数確認されており、犯行が繰り返されていると判断され、同種の余罪の取り調べが本罪の全容解明にも役立つ場合、その限りで本罪での身柄拘束中に余罪について話を聞くことが任意捜査として許容されます。
さらに、本罪と余罪が密接に関係している場合も例外です。
たとえば、複数の窃盗行為が同一手口や短期間のうちにおこなわれていたといった事情があれば、全体像を把握する必要性から、余罪についても併せて取調べがおこなわれることがあります。
なお、被疑者自身が「余罪についても話したい」と申し出た場合には、任意の供述を元にした任意捜査として進められます。
このように、事件単位の原則を前提としつつも、事案の性質や本罪捜査との関連性に応じて、例外的に余罪の任意取り調べがされることがある点は押さえておきましょう。
余罪が発覚する主なきっかけ
余罪取り調べに不安を抱える方にとって、「何をきっかけに余罪が明るみに出るのか」は非常に気になる点だと思います。
実際、余罪は無制限に調べられるわけではなく、発覚には一定の契機があります。
ここでは、余罪が発覚する典型的なケースをわかりやすく解説します。
捜査や取調べの過程で発覚
余罪が発覚するきっかけとしてもっとも多いのは、本罪の捜査中に押収された物品やデータ、証言などから、別の犯罪の存在が疑われる場合です。
たとえば、盗撮やわいせつ事件ではスマートフォンの画像フォルダに本件とは別の被害者の画像が保存されていたり、薬物事件ではSNSやメッセージアプリのやり取りから過去の売買の痕跡が見つかったりするケースがあります。
また、防犯カメラ映像や現場の指紋、押収された所持品など、物理的証拠の分析により、過去の行為が芋づる式に明らかになることも少なくありません。
被疑者や共犯者の自白により発覚
被疑者自身の供述や、共犯者からの供述によって余罪が判明するケースもあります。
とくに複数人でおこなわれた犯行では、ほかの関係者の任意の供述から別件の関与が発覚することは少なくありません。
共犯者の中には、本罪に対する反省の態度の一環として捜査への協力姿勢を示し、余罪について自発的に供述する人もいます。
そのため、「自分が話さなければ大丈夫」と考えていても、別ルートから余罪が浮上する可能性は十分にあるといえるでしょう。
被害届によって発覚
もうひとつの重要なきっかけが、被害者からの新たな被害届です。
報道や警察発表を見た別の被害者が、「自分もこの人物に被害を受けたかもしれない」と考えて通報することで、余罪が浮かび上がることがあります。
特に特殊詐欺や性犯罪のように被害者が複数にわたる場合、逮捕後の報道によって余罪が次々と判明することも珍しくありません。
また、被害届が新たに提出されると、警察はその内容をもとに証拠関係を精査し、必要に応じて再逮捕や追起訴に踏み切ることになります。
余罪によって罪が重くなる?
余罪が発覚したとき、多くの方が気にされるのが「刑が重くなるのか?」という点です。
本罪のみであれば軽い処分で済む可能性がある場合、余罪が加わることで処分が重くなるのではないかと、不安に感じると思います。
ここでは、余罪が処分にどのような影響を与えるのかを、法的観点から解説します。
本罪の裁判では、余罪で処罰されない
まず大前提として、裁判所は公訴事実(起訴された犯罪事実)(本罪)についてのみ審理し、判断を下します。
そのため、余罪が追起訴されていない限り、本罪の裁判のなかで余罪について実質的に処罰されることはありません。
たとえば、被告人が万引きで起訴されていたとしても、「ほかにも同じようなことをしていた」との疑いがあるだけで、その余罪が起訴されていなければ、万引き1件についてのみ裁かれることになります。
この点は、無罪推定の原則や、被告人の防御権の保障という観点からも重要です。
余罪があることで、本罪の量刑が重くなることはある
起訴されていない余罪であっても、「量刑の判断に影響を与える」ことはあり得ます。
たとえば、起訴されている本罪に加えて、過去にも同様の行為を繰り返していた場合、余罪を処罰する目的ではなく、本罪の量刑を決める際の常習性、動機・背景事情、規範意識等として考慮されます。
つまり、余罪そのものによって処罰されることはなくても、「情状」として量刑に不利に働くことがあるということです。
余罪が追起訴された場合、併合罪となり量刑の法律上のルールが変わる
余罪についても追起訴された場合は、「併合罪(へいごうざい)」として、本罪と余罪を合わせて裁かれることになります。
量刑には刑法第47条の併合罪加重規定が適用され、最も重い罪の法定刑の長期にその2分の1を加えた期間まで科すことができます。
たとえば、本罪が懲役5年、余罪が懲役3年だった場合、単独であればそれぞれの刑が科されるところ、併合罪として扱われれば最大で懲役7年6月までの判決が可能になります。
初犯でも余罪があれば、本罪の処分が重くなる可能性がある
本罪について「初犯だから軽く済むだろう」と考える方もいるかもしれませんが、余罪が複数存在する場合、その考えが通用しないことがあります。
たとえ正式な前科がなくても、複数の余罪があることで、「反復的な犯行」と見なされるからです。
その結果、余罪の内容によっては初犯でも実刑の可能性が高まります。
具体的には、余罪のなかに被害金額が高額なものや、被害者が多数いるものが含まれていれば、検察官が余罪も起訴し、処分を重くする方向で動くことがあります。
余罪の捜査が開始されたら、どのような手続きがおこなわれる可能性がある?
余罪の存在が明らかになり、警察や検察が正式に捜査を始めた場合、その後の手続きはどう進んでいくのでしょうか。
ここでは、余罪が立件されたあとに想定される主な流れを整理して紹介します。
【ケース1】本罪とあわせて余罪が起訴された場合
本罪の起訴・不起訴が決まる前に余罪が発覚し捜査が行われ検察が両事件について立証できると判断した場合、本罪とあわせて余罪も起訴されることがあります。
この場合、余罪も起訴された以上は改めて余罪の捜査ために逮捕や勾留がおこなわれることはありません。
なお、起訴後は、裁判所が裁判に出廷させるために必要があると判断した場合に身柄拘束が続きます。
【ケース2】本罪の起訴後に余罪が追起訴される
余罪についての証拠が十分に整っていない場合、まずは本罪のみを起訴し、余罪についてはあとから「追起訴」されることがあります。
この追起訴は、本罪の起訴後も被告人が勾留されたままの状態でおこなわれることが多く、本罪の裁判中に余罪の勾留状や逮捕状が発付されることがあります。
余罪の追起訴がされた場合、当初の本罪の裁判に余罪が併合されて審理されることが多いです。
ただし、例外的ですが、本罪の裁判が終盤であるが追起訴された余罪の証拠調べに時間を要する場合等、被告人の防御権を保護するため必要がある場合には本罪の裁判手続きとは分離し、本罪と余罪を別々の裁判で審理することがあります(刑事訴訟法第313条第2項)。
【ケース3】余罪は不起訴とされ、本罪のみ起訴される
余罪について捜査が行われた結果、余罪が不起訴処分となることがあります。
不起訴の理由としては、以下のような事情が考えられます。
- 犯行を立証する直接的な証拠がない
- 被害届が提出されていない
- 本罪での処分により、社会的制裁としては十分と判断された
- 示談が成立し、被害者が処罰を望んでいない
余罪が不起訴となった場合は、あくまで本罪のみに基づいて裁判がおこなわれることになり、余罪についての法的な判断は下されません。
ただし、前述のとおり余罪の存在が量刑判断に影響する可能性はあるため、「不起訴=本罪の量刑に影響なし」とは限りません。
余罪は自白するべき?
取り調べの中で「ほかにもやっていないのか」と聞かれたとき、黙っているか、正直に話すかで悩まれる方もいると思います。
ここでは、余罪の自白に関する基本的な考え方を解説します。
余罪の自白は義務ではない
まず大前提として、余罪について自白する法的な義務はありません。
憲法第38条では、自己に不利益な供述を強要されない「黙秘権」が保障されており、これは余罪についても同様です。
そのため、取調べにおいて「正直に話さないと不利になる」「認めないと反省していないと見なされる」といったプレッシャーを受けたとしても、余罪に関して黙っている権利はあるということを知っておくべきでしょう。
また、逮捕・勾留中に捜査されているのはあくまで「本罪」であり、逮捕状や勾留状に記載されていない余罪について取調べを受ける義務はありません。
余罪を自白しないことで、罪が重くなってしまう可能性はある
余罪について自白する義務はありませんが、「余罪を隠し通せば絶対に有利になる」とも限らない点には注意が必要です。
もっとも、あとになって確かな証拠とともに余罪が発覚した場合、「取調べの段階で嘘をついていた」「反省していない」と判断され心証が悪化するおそれがあります。
弁護士に相談して、余罪を自白するか検討することが推奨される
余罪があることを自覚している場合は、刑事事件に詳しい弁護士に早い段階で相談し、自身の状況を正確に伝えたうえで、最善の方針を立てることが大切です。
弁護士は、余罪について証拠が今後出てくる可能性が高いかどうかを見極め、最終的に立件される可能性があるかを冷静に分析してくれます。
また、被害者と示談交渉を進められる見込みがあるか、あるいは自白することで不起訴や刑の減軽といった有利な結果が得られる余地があるかどうかといった観点も含めて、判断材料を提供してくれます。
さらに、取り調べで何をどのように話すべきか、どの部分は黙秘してよいかなど、具体的な受け答えのアドバイスも受けることも可能です。
早い段階で弁護士を選任し、余罪にどう向き合うかを専門的な視点で検討しておくことが、結果として自分を守る最善の方法となるでしょう。
余罪捜査が開始されたとき、弁護士に相談・依頼すべき理由
余罪の存在が明らかになり、警察や検察による取調べが始まった場合、「どう対応すればいいのか」「話すべきか否か」など、多くの判断を迫られることになります。
そうした状況において、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談・依頼することは、非常に重要な意味を持ちます。
ここでは、余罪捜査が始まった段階で弁護士を頼るべき具体的な理由を解説します。
自白すべきかを含め、今後の対応について適切な助言が得られる
余罪がある場合、本罪の取調べでどのように話すか、あるいは黙秘すべきかを一人で判断するのは困難です。
その点、弁護士であれば、取調べの進行状況や証拠の有無、余罪がどの程度追及される可能性があるかなどを踏まえた対応方針を検討してくれます。
余罪の自白が量刑に与える影響や、黙秘を選択した場合に生じるリスクについても、具体的な見通しを含めて助言してくれるため、不安な取調べにも落ち着いて向き合えるようになります。
不当な取調べ・身体拘束を避けるための活動をしてもらえる
余罪が複数ある場合、再逮捕や勾留延長などによって、長期間にわたり身体拘束が続くおそれがあります。
さらに、取調べの中で「早く白状しろ」「隠していてもムダだ」といった心理的圧力をかけられることも考えられるでしょう。
このような不当な取調べが疑われる場合でも、弁護士が選任されていれば、勾留の不服申立てや取調べ方法に対する抗議など、適切な手続を講じてくれます。
示談により不起訴・刑の減軽を目指せる
余罪が複数ある場合でも、被害者との示談が成立すれば、不起訴や略式命令など比較的軽い処分にとどめられる可能性があります。
ただし、複数の被害者がいる場合には、それぞれに対する対応が異なり、示談交渉の進め方にも工夫が求められます。
その点、弁護士であれば、どの余罪について先に示談を優先すべきか、どのような内容で交渉すべきかといった点も踏まえて動いてくれるため、結果として刑事処分の軽減や社会復帰への道筋を早めることにつながるでしょう。
さいごに|余罪捜査が不安であれば弁護士に相談を!
「余罪も調べられるのかな」「また逮捕されるかも」と、不安な気持ちを抱えている方も多いと思います。
余罪捜査は本来ルールがありますが、場合によっては例外的に取調べが進むこともあり、どう対応すべきか迷ってしまうのも無理はありません。
そんなときこそ、早めに弁護士に相談することが大切です。
弁護士は、話すべきか黙っておくべきか、示談はできるかなど、今の状況に合ったアドバイスをくれます。
不安を一人で抱えず、先の見通しを立てるためにも、専門家の力を借りましょう。
「こんなことで相談していいのかな…」と思うかもしれませんが、弁護士はあなたの味方です。
少しでも気になることがあれば、まずは一歩を踏み出してみてください。