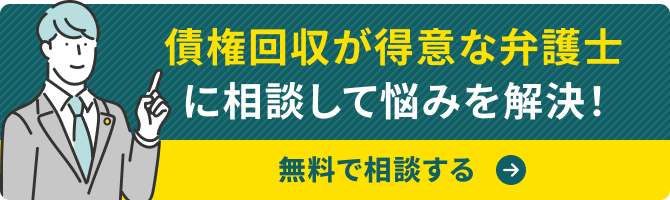病院における未収金問題は、経営に大きな影響を与えかねない重要な課題の一つです。
患者の未払い状態が続けば、資金繰りが悪化し、安定した医療サービスの提供が難しくなる可能性もあります。
そのような事態に陥るのを防ぐためにも、あらかじめ対策マニュアルを準備しておくのが望ましいでしょう。
本記事では、病院における未収金の対策マニュアルを原因別に紹介するほか、事前に準備しておきたい予防策や発生後の回収手順を解説します。
安定した病院経営を維持するためにも、未収金対策を強化しておきましょう。
【原因別】病院ができる基本的な未収金対策マニュアル
患者が受診後に診療費を支払えない理由はさまざまです。
支払う意思があるのに緊急受診であったり、労災保険や自賠責保険を利用したりするために支払えない場合もあれば、始めから支払う意思がない場合もあります。
そのため、病院側は未払いの原因に合わせた対応を取らねばなりません。
下表では、主な未収金の発生原因と、取るべき内容についてまとめました。
自院でマニュアルを策定する際の参考にしてください。
| 未収金の原因 | 基本的な対応内容 |
|---|---|
| 緊急受診など突発的な事態による保険証不携帯 | ・住所・氏名・被保険者(世帯主)、連絡先電話番号(自宅・勤務先)の確認 ・預り金の徴収 ・未納額の告知 ・次回診療までの清算申し渡し ・支払予定日(保険手続きなどの完了)の確認 |
| 緊急受診など突発的な事態による現金不携帯 | ・住所・氏名・被保険者(世帯主)、連絡先電話番号(自宅・勤務先)の確認 ・未納額の告知 ・次回診療までの清算申し渡し ・支払予定日(保険手続きなどの完了)の確認 |
| 労災や自賠責の適用者かつ手続き完了前 | ・住所・氏名・被保険者(世帯主)、連絡先電話番号(自宅・勤務先)の確認 ・預り金の徴収 ・未納額の告知 ・支払予定日(保険手続きなどの完了)の確認 ・公的な救済制度の利用などについてアドバイスをする |
| 支払う意思があるもののお金がないか不足している | ・住所・氏名・被保険者(世帯主)、連絡先電話番号(自宅・勤務先)の確認 ・未納額の告知 ・次回診療までの清算申し渡し ・支払予定日(保険手続きなどの完了)の確認 ・支払誓約書(連帯保証人)を提出してもらう ・公的な救済制度の利用などについてアドバイスをする |
| 資格喪失などの理由による保険証の不携帯 | ・住所・氏名・被保険者(世帯主)、連絡先電話番号(自宅・勤務先)の確認 ・預り金の徴収 ・未納額の告知 ・次回診療までの清算申し渡し ・支払予定日(保険手続きなどの完了)の確認 ・支払誓約書(連帯保証人)を提出してもらう ・公的な救済制度の利用などについてアドバイスをする |
| 生活保護などの受給資格をもたない困窮者 | ・住所・氏名・被保険者(世帯主)、連絡先電話番号(自宅・勤務先)の確認 ・未納額の告知 ・次回診療までの清算申し渡し ・支払予定日(保険手続きなどの完了)の確認 ・支払誓約書(連帯保証人)を提出してもらう ・公的な救済制度の利用などについてアドバイスをする |
| 最初から支払う意思がない悪質な患者 | ・住所・氏名・被保険者(世帯主)、連絡先電話番号(自宅・勤務先)の確認 ・未納額の告知 ・次回診療までの清算申し渡し ・支払予定日(保険手続きなどの完了)の確認 ・支払誓約書(連帯保証人)を提出してもらう ・公的な救済制度の利用などについてアドバイスをする |
【参考】京都私立病院協会 未収金対策委員会「未収金対策マニュアル」
また、支払い能力がないために未払いとなっている患者へは、次のような公的な救済制度の紹介が有効な場合もあります。
| 公的制度 | 概要 |
|---|---|
| 高額療養費制度 | 同じ月内にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合に、一定金額を超えた部分についてあとから払い戻してもらえる制度 |
| 高額療養費貸付制度 | 高額療養費制度による払い戻しの前に、見込み額の8割程度を無利子で借りられる制度 |
| 一部負担金減免制度 | 災害や失業などの特別な理由によって収入が大幅に減少したために、医療費の支払いが困難な場合に、一部減免や徴収の猶予を受けられる制度 |
| 付加給付制度 | 大手企業など一部の健康保険組合が、設定された自己負担限度額を超過した場合に一部を払い戻す制度 |
| 生活保護制度 | 経済的に困窮し生活が困難な人に対し、国が最低限の生活を保障する制度 |
病院が事前に準備しておくとよい未収金予防策
医療費の滞納を予防するには、マニュアルの作成に加えて、次のような対策を講じておくのが有効です。
- 複数の決済方法を用意しておく
- 患者が事前に医療費を確認できる一覧表を用意しておく
- 迅速かつ適切に督促がおこなえるよう、手順をマニュアル化しておく
- 保証金・連帯保証の対応フローを準備しておく
- 必要に応じ分割払いにも応じるようマニュアル化しておく
それぞれの予防策について、以下で詳しくみてみましょう。
複数の決済方法を用意しておく
「現金以外の支払い方法を導入していない」という場合は、クレジットカードやQR決済の導入を検討しましょう。
最近はキャッシュレス決済が浸透しており、経済産業省が2023年3月に発表した「消費者実態調査の分析結果」によると18歳〜29歳の方で現金を「まったく持ち歩かない」と回答した方は26%にのぼります。
現金の持ち合わせがなくても、キャッシュレスであれば支払ってもらえる場合もあるでしょう。
また、キャッシュレス決済の導入は外国人観光客の未収金対策としても有効です。
すでに導入している場合でも、対応可能なQR決済を増やすなど、より積極的に取り入れることを検討するとよいでしょう。
患者が事前に医療費を確認できる一覧表を用意しておく
未収金が発生する背景の一つとして、患者が診療内容に対する医療費に納得できないケースがあります。
このような事態の発生を防ぐには、医療費の概算がわかる一覧表を用意しておくのがよいでしょう。
とくに、高額な費用がかかる検査や手術については、診療前に一覧表を示しながら患者に説明しておくのが得策です。
事前にどれくらい請求されるかがわかっていれば、不満を抱かれにくく、支払いに応じてもらいやすいはずです。
また、経済的な問題があり、支払いの準備が難しいという患者に対しては、公的な救済制度を案内するのもよいでしょう。
迅速かつ適切に督促がおこなえるよう、手順をマニュアル化しておく
未収金の回収はスピードが大切です。
未払いが発生したら速やかに督促を開始し、滞納期間に応じて適切な対応を取る必要があります。
しかし、何をすればよいのかがわからなければ、迅速な対応は難しいものです。
そのようなリスクを低下させるためにも回収手順をマニュアル化し、職員全員で共有しておくことが大切です。
誰でもわかるようにまとめておけば、担当者が変わってもスムーズに対応できます。
改善点も把握しやすいため、定期的にブラッシュアップすれば回収率のアップにもつながるでしょう。
保証金・連帯保証の対応フローを準備しておく
医療費がとくに高額になる場合には、保証金や連帯保証による対策と、対応の流れを決めておくのも効果的です。
保証金とは、治療や入院前に収めてもらうお金です。事前にお金を納めてもらうことで、未収金の発生防止につながります。
また、患者にとっても、あらかじめ治療費の目処を把握できるため、安心して治療を受けられる点がメリットです。
ほかにも、患者に連帯保証人を用意してもらうのも有効です。
連帯保証人を立てておくことで、患者本人が支払いに応じなくても、連帯保証人に治療費の支払いを求められます。
入院や手術などの高額な治療をおこなう前に保証契約書を用意しておき、付き添いで来院している場合は目の前でサインしてもらいましょう。
難しい場合は患者に持ち帰ってサインをもらってもらい、必ず治療前に提出してもらうようにします。
必要に応じ分割払いにも応じるようマニュアル化しておく
治療費の分割払いにも応じられるようにしておくと、未収金を減らすことにつながる可能性があります。
支払う意思はあるものの、経済的な理由から分割払いを希望する方向けに、窓口で医療ソーシャルワーカーなどに相談できる体制を整えておくとよいでしょう。
また、分割払いの支払いが滞った場合の対応マニュアルもあらかじめ作っておくことをおすすめします。
ただし、外国人観光客の場合は、分割払いによる対応は避けるのが無難です。
海外からの振り込み手数料は高額であるため、帰国後に支払ってもらえない可能性が高いからです。
家族や友人、銀行に借りるなど、別の方法を検討してもらうようにしましょう。
未収金が発生した場合の主な対策マニュアル | 病院が取り立てをする手順
未払い金の回収マニュアルを作成するにあたって「未収金が発生した場合の標準的な対応が知りたい」という担当者もいるでしょう。
ここではそのような方に向けて、未収金の取り立てについての一般的な手順を紹介します。
未収金を定期的に管理する
未収金を減らすためには、未払いの発生にいち早く気づくことが大切です。
支払い期日の翌日には必ず入金を確認し、入金管理システムや台帳に記録して管理しましょう。
ほかの業務によってあと回しにならないよう、担当者を決め、ルーティン化しておくことが大切です。
【未収金発生から1週間~2週間】電話などで督促
期日の翌日までに入金がなければ、速やかに患者へ連絡し、早急に支払ってもらえるよう督促をおこないましょう。
まずは電話やメール、手紙などで「支払いの確認」という形で連絡をするのがおすすめです。
手紙の場合は、誓約書のコピーも同封しておきます。
督促の期日までに支払いがなければ、1週間~2週間にわたって何度か督促の連絡をおこなってください
【未収金発生から1~2ヵ月】督促状や催促書の送付
メールや手紙などによる督促をおこない、1ヵ月経っても支払いがなければ、督促状や催促書を送付して請求します。
これらの書類は厳格な印象を与えられるので、支払いに応じてもらえるケースもあるはずです。
また、督促状には法的手続きをとることを前もって知らせる効果もあるので、この時点で支払に応じてもらえる可能性は高いでしょう。
病院が未収金回収をおこなうための督促状例文【弁護士監修済】
ここでは、「どんな文面にすればよいのかわからない」という方のために、督促状の例文を用意しました。
なお、内容は弁護士が監修しているので、そのまま使用していただくことができます。
|
令和○年○月○日 督促状 A 様 ○○病院○○ 平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 令和〇年〇月〇日の外来治療に係る医療費(〇円)のお支払いを頂いておりません。つきましては令和〇年〇月〇日までに下記口座に振込む方法でお支払いをお願いいたします(振込手数料はご負担ください)。 ご不明点がございましたら、担当窓口(担当者名・電話番号)までご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。 また、期限内にお支払い頂けない場合は、やむをえず法的手続きに移行する旨も了承ください。 敬具 (銀行の振込先口座情報) |
督促状に必ず記載すべき項目
督促状を作成する際、以下の項目は必ず記載するようにしましょう。
- 表題(「督促状」など)
- 作成日
- 宛名
- 差出人と捺印
- 未払い金額
- 支払い期限
- 法的手段の告知
【未収金発生から3ヵ月】内容証明で催告書を送付
督促状を送っても支払いに応じてもらえない場合は、催告書を送付します。
催告書は、法的手段へ移行する前の最終通告書面です。
内容証明郵便を利用して送れば、差出人・宛先・送付日・内容を郵便局に証明してもらえるため、法的手段へ移った際に、督促の事実を立証する証拠として利用できます。
【未収金発生から6ヵ月】法的手段
催告書に記載した期限までに支払いがなければ、いよいよ法的手段に移行します。
病院の未払いを回収するための法的手段としては、具体的には以下のような方法が考えられます。
| 法的手段 | 内容 |
|---|---|
| 支払督促 | 裁判所から督促状を送付して支払いを命じてもらう手続き。 相手がそれでも支払わなければ「仮執行宣言付支払督促」により強制執行も可能。 |
| 民事調停 | 調停委員が間に入って当事者同士での話し合いによる解決を目指す手続き。 |
| 少額訴訟 | 請求額が60万円以下である場合に利用できる手続き。 原則として1度の期日で完結する。 |
| 民事訴訟 | 請求額が60万円を超える場合、また、支払督促で異議を申し立てられた場合に利用する通常の訴訟手続き。 期日は複数回にわたるケースが多く、終結までに時間がかかる。 |
強制執行をおこなう
裁判所から支払いを命じられても従わない場合は、相手方の資産を差し押さえて、強制的に未収金を回収します。
ただし、強制執行手続きをしたからといって、必ずしも未収金を回収できるとは限りません。
相手方に資産がなければどうしようもないため、事前に調査のうえ実行する必要があります。
弁護士やサービサーへ未収金の取り立てを委託する方法も検討する
病院スタッフが自ら未収金の取り立てをおこなうのは大変です。
普段の業務に加わって時間も手間もかかるうえ、知識や経験がなければなかなか回収が進まないリスクもあります。
そのため、多少の費用をかけてでも、回収のプロである弁護士やサービサーへ委託することも検討しましょう。
弁護士やサービサーへ依頼すれば、文書の作成や手続きはもちろん、債務者との交渉も任せられます。
スタッフの負担を大幅に減らせるうえ、回収できる可能性も高まるでしょう。
病院が未収金の回収をおこなう際の注意点
患者へ未収金を請求する際は、次の点に注意しましょう。
患者の生活に支障を与える取り立ては控える
未払いがあるからといって、常識の範疇を超えて取り立ててはいけません。
早朝や深夜の電話や訪問、正当な理由のない職場への連絡など、患者の生活に支障を与えかねないおこないは違法行為です。
なかなか支払いに応じてもらえない場合は、法的手段を取るなど、真っ当な方法で請求しましょう。
未収金のある患者でも、基本的には診療を拒否できない
診療費を支払わないからといって、来院した患者の診療を拒否することはできません。
医師には法律によって応召義務が課せられており、診療時間内に診察を求められれば、原則として応じなければならないからです。
緊急性がない場合、治療費を支払う意思のない患者の診療拒否は可能
医師には応召義務があるとはいえ、理不尽な患者のおこないまで受け入れる必要はありません。
そのため、治療費を支払う意思のない患者に対しては、緊急性がない限り診療を拒んでも問題にはならないでしょう。
ただし、緊急性の高い患者の処置を治療費の不払いを理由に拒むと、人道に反すると解釈され、責任を問われる可能性があります。
未収金には5年の消滅時効がある
未収金には消滅時効があり、支払期限から5年が経過すれば請求できなくなります。
「未収金の存在に気づかず、請求できなくなってしまった」ということのないよう、普段から定期的に未収金を管理するようにしましょう。
万が一、時効期限が迫っている場合は、時効中断措置を取る必要があります。
時効が成立するまでに支払督促や訴訟、調停といった裁判所手続きを申し立てましょう。
また、内容証明郵便で催告書を送付すれば、時効を6ヵ月間延長できます。
これらの対応には、法的な知識や手続きが必要なので、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
さいごに | 病院の未収金対策については弁護士へ相談を!
未収金問題に適切に対応するには、あらかじめ対策マニュアルを準備しておくことが大切です。
事前に準備しておけば、実際に未払いが起きた場合にスムーズに対処できますし、スタッフ全員で共有しておくことで、担当者が変わっても問題なく対応できます。
しかし、あまりに長期間未払い状態が続き、督促状や催告書などの書面の作成や裁判所手続きが必要になると、スタッフにとって大きな負担となるでしょう。
通常業務に支障をきたさないようにするためにも、未収金の回収は弁護士に依頼するのが賢明です。
弁護士に依頼すれば、全ての手続きを任せられるので、スタッフの負担を増やすことなく、未収金問題を解決できるでしょう。
より安定した病院経営を目指すためにも、未収金対策は弁護士へ相談してください。