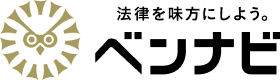遺産相続の話し合いのなかで「生前に多くの財産をもらっていた人がいて不公平では?」と感じたことはありませんか。
このようなケースに関係してくるのが、「特別受益(とくべつじゅえき)」という制度です。
特別受益とは、相続人のうち一部の人が被相続人(亡くなった人)から生前贈与など特別な利益を受けていた場合に、その分を相続分で調整する仕組みのことをいいます。
本記事では、特別受益の基本的な意味や、特別受益に当たる具体的な例、相続分の計算方法までをわかりやすく解説します。
相続トラブルを避けたい方や、公平な遺産分割を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
特別受益とは?一部の相続人だけが被相続人から受けた利益のこと
特別受益とは、相続人のうち特定の人だけが被相続人から特別な利益を受けていた場合に、その利益分を考慮して相続分を調整する制度のことです。
たとえば、生前に家を建ててもらった、結婚資金の援助を受けた、事業資金を贈与されたといったケースがこれに当たります。
こうした利益を受けた相続人がほかの相続人と同じ割合で遺産を受け取ると不公平が生じるため、特別受益の分を遺産の前渡しとして扱い、相続分を計算し直す(持ち戻し計算)のが基本です。
特別受益の制度は、相続人間の公平を保つために設けられたものであり、相続トラブルを防ぐうえでも重要な考え方といえます。
特別受益に関する民法条文
特別受益に関しては、民法第903条に以下のように明記されています。
(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
第九百四条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索
特別受益とみなされる利益は大きく分けて3種類
特別受益として扱われる利益は、大きく分けると「遺贈」「死因贈与」「生前贈与」の3種類です。
ここでは、それぞれの特別受益について具体例を挙げながら詳しく解説します。
1.遺贈 | 遺言によって与えられた遺産
遺贈とは、被相続人が遺言によって特定の相続人、または相続人以外の第三者に財産を与えることを指します。
相続において、遺言の内容は被相続人の意思として尊重されるべきです。
とはいえ、相続人の一人が多額の遺贈を受けた場合、ほかの相続人にとって不公平が生じやすくなるため、特別受益として扱われる可能性があります。
たとえば、父の遺言に「長男に自宅を遺贈する」と記載されていた場合、自宅自体は長男が相続することになります。
しかし、ほかにも兄弟姉妹がいる場合、自宅以外の財産を等分して相続すると不公平となるため、遺贈された自宅の価値を相続財産に含めたうえで相続割合を調整することになるでしょう。
2.死因贈与 | 被相続人の死亡を条件に贈与された財産
死因贈与とは、生前に結んだ「自分が亡くなったらこの財産をあなたに贈与する」という契約に基づいておこなわれる贈与のことです。
遺贈と似ていますが、遺贈は遺言に基づく一方で、死因贈与は契約による点で異なります。
たとえば、父が生前に「私が亡くなったら自宅を与える」という契約を長男と結んだ場合、父の死後にその効力が生じます。
このような死因贈与も民法上は特別受益として扱われ、ほかの相続人の相続分を調整する対象になります。
3.生前贈与 | 被相続人の生前に贈与された財産
生前贈与は、被相続人が存命中に特定の相続人へ財産を渡すことを指します。
ただし、生前贈与の全てが特別受益にあたるわけではありません。
生前贈与のうち特別受益にあたるのは以下の3つです。
- 婚姻のための贈与
- 養子縁組のための贈与
- 生計の資本としての贈与
それぞれの贈与について、詳しく見ていきましょう。
婚姻のための贈与
婚姻に伴って被相続人から相続人へ生前贈与された財産は、特別受益として扱われることがあります。
たとえば、結婚持参金や支度金など、ある相続人の婚姻のために当事者間で直接やり取りされる金銭が代表的です。
とくに数百万円規模の援助を受けた場合、ほかの相続人との間で大きな不公平が生じるため、その分を相続財産に含めて遺産分割する必要があります。
ただし、金額が少額で扶養の範囲内と認められる場合は特別受益にあたりません。
養子縁組のための贈与
養子縁組に伴う支度金や特別な援助も特別受益とされることがあります。
たとえば、養子縁組にあたって数百万円の資金を与えた場合や、住居の準備費用など特別な援助をおこなった場合です。
これらは扶養義務を超える性質を持つため、相続時に公平性を保つために特別受益として調整されます。
ただし、金額によっては特別受益として扱われないケースも少なくありません。
単なる日常の生活支援ではなく「将来的な独立や生活基盤を整える目的」の贈与であるかどうかが、特別受益に含まれるかどうかの判断基準となることを覚えておきましょう。
生計の資本としての贈与
生計の資本とは、生活の基盤を支えるために必要な資金のことを指します。
たとえば、住宅購入資金や事業の開業資金などが代表例です。
これらは「一度きりで高額な援助」となるケースが多いため、特別受益に該当します。
たとえば、父親が長男にマンション購入資金として2,000万円を贈与した場合、ほかの相続人との公平を確保するため、相続時にはその額を遺産に持ち戻して計算します。
特別受益に当たらない生前贈与
特別受益は、一部の相続人が被相続人から不公平に財産を受け取っている場合に考慮されます。
しかし、全ての生前贈与が特別受益にあたるわけではありません。
以下では、特別受益に当たらない生前贈与について、具体例を挙げながら解説します。
遺言書などで「特別受益の持ち戻し免除」の意思表示をされた贈与
民法第903条3項では、同条2項の「遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。」という規定に対し、「被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。」と定めています。
これはつまり、被相続人が「持ち戻し免除」の意思を示した場合、その贈与は特別受益に含まれないということです。
たとえば、父が「生前、長男に自宅購入資金として援助した2,000万円について、特別受益としての持ち戻しを免除する」と遺言書に明記した場合、この援助は持ち戻しの対象外となります。
意思表示は遺言書のような書面で残すのが基本ですが、法律で形式が定められているわけではありません。
そのため、口頭で持ち戻し免除を宣言した場合でも、明確に確認できる事情があれば認められることもあります。
ただし、意思表示があいまいだとトラブルに発展する可能性があるため、できれば公正証書遺言などで正式に残すことが望ましいでしょう。
相続人以外に対する贈与
特別受益は、あくまで「共同相続人間の公平性を保つための制度」です。
そのため、相続人以外に対する贈与は特別受益には該当しません。
たとえば、被相続人が生前に孫へ学資資金を援助した場合や、友人へ生活資金を贈与した場合は、特別受益として考慮することはできないのです。
ただし、相続人以外に対する贈与は「遺留分侵害額請求」の対象になる可能性があるため、完全に無関係とはいえません。
子どもたちのなかで「なぜ孫には贈与したのに自分たちにはなかったのか」と不満が出ることも多いでしょう。
その際は、特別受益として持ち戻しを請求するのではなく、遺留分侵害額請求の可能性を検討する必要があります。
【関連記事】遺留分侵害額請求とは?期限や方法、遺留分の割合・計算方法を解説
おしどり贈与(贈与税の配偶者控除が適用される贈与)
「おしどり贈与」とは、婚姻20年以上の夫婦間で居住用不動産またはその購入資金を贈与した場合に、2,000万円まで贈与税が非課税になる制度の俗称です。
正式名称は「贈与税の配偶者控除」といいます。
この制度を利用しておこなわれた贈与は、基本的に老後の生活安定を目的とするものと考えられ、特別受益の持ち戻し免除の意思表示があったと推定されます。
たとえば、父が母にマイホームを贈与した場合、これは家族の生活を維持するための行為であり、相続人間の公平性に直接関わるものではないと考えられます。
ただし、おしどり贈与を利用して形式的に多額の財産を移転した場合、ほかの相続人から不満が出る可能性があるため、事前に相続人全員に説明しておくことが大切です。
「黙示の持ち戻し免除」とみなされる贈与
遺言書などによって持ち戻し免除の意思を明確に示していなくても、贈与の内容から持ち戻し免除と判断される場合があります。
これを「黙示の持ち戻し免除」といいます。
たとえば、以下のような場合は、黙示の持ち戻し免除が認められる可能性があります。
- 家業を継承する相続人が、相続分以外に農地や店舗などの財産を相続した
- 一部の相続人が、被相続人に対して介護をしていたなど贈与の見返りがあった
- 相続人に、相続分以上の財産を必要とする特別な事情がある
黙示の持ち戻し免除が認められるかどうかは、贈与の内容や金額、被相続人と相続人との関係性、経済状況などを総合的に考慮して判断されます。
黙示の持ち戻し免除を巡って遺族間でトラブルが起こることも多いため、遺言書などで特別受益の持ち戻し免除の意思を明確に示しておくのがおすすめです。
そのほか特別受益に当たらない利益
特別受益は、被相続人から特定の相続人が受けた贈与を相続分に反映させる制度ですが、日常生活に必要な援助や、慣習上当然とされる援助は特別受益に含まれません。
特別受益に当たらない利益として、具体的には以下のようなものが挙げられます。
| 名目 | 概要 |
|---|---|
| 結納金・結婚式費用 | 結納金や結婚式費用は、子どもの婚姻に伴い親が援助するのが社会通念上一般的とされます。たとえば結婚式費用として数百万円を援助した場合でも、特別受益に当たらない可能性があります。 |
| 大学の入学金・学費 | 大学への進学費用は、教育を受けさせる親の扶養義務の範囲内とみなされます。そのため、進学時に入学金や授業料を親が負担しても、特別受益には当たりません。 |
| 生活費の援助 | 被相続人が子どもの生活費を援助していた場合、通常は扶養義務に基づくものと考えられます。たとえば、独立するまでの仕送りや一時的な生活費の補填などが含まれます。 |
| 新築祝い | 家を新築した際に親から新築祝いとして資金を贈与された場合も、数十万円程度と慣習的なお祝いの範囲に収まるものであれば特別受益には当たりません。 |
| 入学祝い | 子や孫の入学祝いも、慣習的なお祝い行為として扱われます。 |
| 死亡保険金 | 被相続人が契約者・被保険者で、相続人が受取人となる生命保険金は、民法上「特別受益」には当たりません。死亡保険金は相続財産ではなく「受取人固有の財産」とされるためです。 |
特別受益がある場合の相続分の計算方法と計算例
特別受益がある場合、相続人間の公平を保つために「持ち戻し」という計算がおこなわれます。
これは、被相続人が特定の相続人に対して生前に贈与した財産を「みなし相続財産」として加算し、その合計額を基準に法定相続分を計算する方法です。
そのうえで、特別受益を受けた相続人の分から生前贈与額を差し引いて最終的な取り分を確定させます。
以下では、具体的な計算手順について、例を挙げながら見ていきましょう。
1.「みなし相続財産」を計算する
最初におこなうのは、被相続人が亡くなった時点の財産に特別受益額を加算する作業です。
これにより、相続人全員で分けるべき本来の財産総額が明らかになります。
たとえば、父親が残した現金が5,000万円、さらに長男が生前に受け取っていた特別受益が1,000万円分あったとします。
この場合、相続開始時点の財産5,000万円に特別受益額1,000万円を加算し、合計6,000万円が「みなし相続財産」として計算されます。
ここで重要なのは、実際に現金として存在するのは5,000万円ですが、相続の公平を図るために遺産分割では6,000万円を基準とする点です。
これにより、贈与を受けていない長女や次男が不利益を被らないように調整されます。
2.各相続人の相続分を求める
次に、算出された「みなし相続財産」を基準に法定相続分を計算します。
相続人が長男・長女・次男の3人であった場合、それぞれの法定相続分は1/3ずつです。
したがって、みなし相続財産が6,000万円だった場合は、3で割って2,000万円が各人の相続分となります。
ただし、長男はすでに1,000万円を特別受益として受け取っているため、この2,000万円からその分を差し引き、最終的に相続できるのは1,000万円です。
一方、特別受益を受けていない長女と次男は、それぞれ2,000万円ずつ相続できます。
結果として、長男1,000万円(+生前に受けた贈与1,000万円)、長女2,000万円、次男2,000万円となり、公平な分配が実現できます。
特別受益は証拠がないと主張できない?
一部の相続人の特別受益を主張する際、当事者同士で話し合って解決できるのであれば、客観的な証拠がなくても特別受益を考慮してそれぞれの相続人を自由に決められます。
ただし、贈与を受けた相続人が特別受益を認めず、調停や裁判に発展する場合は、被相続人から特定の相続人へ財産が贈与された事実を客観的に示す証拠が必要です。
特別受益とみなされる財産は、数百万円〜数千万円と金額も高いケースが多く、話し合いだけで解決しようとするとトラブルに発展しがちなのも事実です。
少しでもスムーズに遺産分割協議を進めるためには、証拠を用意しておくとよいでしょう。
特別受益の証拠となりえるもの
特別受益があったことを証明するためには、以下のような証拠を集めましょう。
| 資料 | 概要 |
|---|---|
| 贈与契約書や遺言書 | 明確に金銭や不動産の贈与が記載されていれば、強い証拠になります。遺言書に「特別受益として扱う」との記載があれば、より確実です。 |
| 故人の銀行口座の取引履歴 | 被相続人の口座から相続人の口座にまとまった金額が振り込まれている場合、その資金が生活費ではなく特別受益であることを示せます。 |
| 不動産登記簿謄本 | 被相続人の名義から相続人へ不動産が移転登記されていれば、贈与の事実が明らかです。 |
| メールや手紙などのやり取り | 「結婚資金として渡す」「開業のために援助する」といった文言が残っていれば、特別受益を示す強い証拠となります。 |
| 車検証 | 自動車の贈与が疑われる場合は、車検証や売買契約書が特別受益の証拠となります。 |
これらの証拠をできるだけ集めて提示することが、特別受益を認めてもらうために重要です。
特別受益に時効はある?何年前のものまで主張できる?
特別受益による持ち戻しは民法第903条に基づく仕組みであり、時効によって消滅することはありません。
ただし、相続開始から長期間が経過している場合や、遺留分を巡る争いでは法律上の制限が設けられるケースがあります。
具体的なケースについて、以下で詳しく見ていきましょう。
相続開始が10年以上前であれば例外的に特別受益の主張はできない
2019年の相続法改正により、相続開始から10年以上が経過している場合、相続人に対する生前贈与を特別受益とみなすことはできなくなりました。
なお、改正された条文は令和5年4月に施行されており、施行前に開始した相続にも適用されます。
ただし、混乱を避けるため、施行日から5年間(=令和10年3月末まで)は猶予期間が設けられています。
たとえば父親が2010年に亡くなっていた場合、2025年になってから兄が受けた生前贈与を持ち戻して遺産分割をやり直すことはできません。
遺留分を計算する際の特別受益は例外的に相続発生から10年以内のものに限る
遺留分とは、法定相続人にあたる配偶者や子どもが最低限保証されている相続分のことです。
被相続人の生前贈与によって遺留分以下の相続分しか受け取れない場合は、生前贈与を受けた人に対して遺留分侵害額請求をすることで遺留分を確保できます。
ただし、遺留分を計算する際に特別受益とみなせるのは、相続開始前10年以内の贈与に限定されます。
たとえば、以下のようなケースで考えてみましょう。
- 父が亡くなった際の相続財産が3,000万円
- 相続人は長男と次男の2人
- 長男に対して1,000万円の生前贈与があった
この場合、長男への生前贈与がいつおこなわれたかによって遺留分の計算結果が以下のように変わります。
| 生前贈与が相続発生から10年以内 | 生前贈与が相続開始から10年以上前 |
|---|---|
| 1.生前贈与分も特別受益として相続財産に含めて考えるため、相続財産は3,000万円 + 1,000万円 = 4,000万円 2.全体の遺留分は相続財産の2分の1なので2,000万円 3.兄弟2人で遺留分を分割するため、遺留分はそれぞれ1,000万円 |
1.生前贈与分は遺留分計算には含まれず、相続財産は3,000万円とする 2.全体の遺留分は相続財産の2分の1で1,500万円 3.兄弟2人で遺留分を分割し、遺留分はそれぞれ750万円 |
特別受益がある場合の遺産分割の流れ
ここでは、特別受益がある場合の遺産分割の流れを紹介します。
1.遺産分割協議で特別受益の持ち戻しを主張する
特別受益が疑われる場合、まずは相続人同士で開かれる遺産分割協議でその内容を主張します。
特別受益の持ち戻しを主張する場合は、贈与契約書、振込明細、領収書、または関係者の証言などの証拠を用意しておくとほかの相続人にも納得してもらいやすくなるでしょう。
相続人全員が納得できれば、その内容を反映した遺産分割協議書を作成し、相続登記や預金の払戻しなどを進めます。
しかし、特別受益の有無や金額を巡って争いが起こることも多く、話し合いが平行線をたどる場合も少なくありません。
その場合、次のステップである家庭裁判所での調停に進むことになります。
2.遺産分割協議で合意できない場合は遺産分割調停を申し立てる
遺産分割協議で合意が得られなかった場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てましょう。
調停では中立的な立場にある調停委員が間に入り、当事者同士の主張を整理しながら合意を目指します。
相続人全員の同意が成立すれば、その内容は調停調書に記録され、相続人は調停調書に従って遺産分割を実施していきます。
一方で、対立が激しい場合や証拠が不足して折り合いがつかないときには、調停が不成立となり、審判へと移行することになります。
3.調停が不成立であれば遺産分割審判へ移行する
調停でも合意に至らなかった場合、家庭裁判所は審判によって遺産分割の方法を決定します。
審判は裁判官の判断によって強制的に分割内容が決められるため、当事者の希望がそのまま反映されるとは限りません。
特別受益があるかどうか、持ち戻しの範囲や金額などについても、提出された証拠をもとに裁判所が判断します。
たとえば「特別受益にあたるはずの結婚資金が証拠不足で認められなかった」などのケースもあり得るでしょう。
しかし、審判で決まった内容には法的拘束力があるため、相続人はこれに従わなければなりません。
審判の内容に不服があれば高等裁判所へ即時抗告が可能ですが、時間や費用の負担は大きくなります。
そのため、可能な限り協議や調停の段階で解決を目指すのが現実的です。
特別受益に関してよくある質問
ここでは、特別受益に関してよくある質問をまとめました。
特別受益による相続トラブルを避けたい人はぜひ参考にしてください。
生命保険・死亡退職金は特別受益に当たらない?
生命保険金や死亡退職金は、原則として特別受益には該当しません。
これらは被相続人の死亡を原因として相続人が受け取る「相続財産」ではなく、保険契約や会社規定などに基づく「受取人固有の財産」とされるためです。
特別受益に相続税は課税される?
特別受益は遺産分割における相続分の計算で考慮されるものであり、特別受益自体が直接相続税の課税対象になるわけではありません。
相続税の対象となるのは、相続開始前7年以内の贈与や、相続時精算課税制度による贈与など、相続税法で定められたものに限られます。
遺産分割における相続分と相続税の計算は混同しやすいため、税理士や弁護士などの専門家に相談することが望ましいです。
さいごに|特別受益はトラブルの種!まずは弁護士に相談を!
本記事では、相続時に特別受益とみなされる利益や、特別受益があった時の相続分の計算方法などについて詳しく解説しました。
特別受益は、被相続人から一部の相続人だけが受けた利益を遺産分割に反映させる仕組みです。
遺贈や死因贈与、生前贈与などが対象となり得ますが、婚姻費用や学費、生活費の援助といったものは特別受益に含まれない場合もあります。
しかし、特別受益については、証拠の有無や持ち戻し免除の意思表示があるかどうかなど、個々のケースで判断する必要があり、相続人同士での主張が食い違うとトラブルに発展しやすい問題です。
そのため、特別受益が疑われる場合は、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士は専門知識に基づいた判断をしてくれるため、円満な解決へと近づけるでしょう。