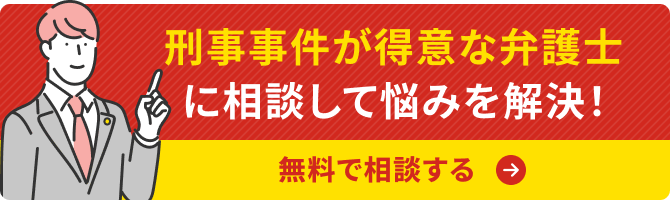「罪を犯してしまい、このままでは前科がついてしまう…前科がつくとどんなデメリットがあるのだろうか?」と不安に陥っている方もいるでしょう。
前科がつくと以下のようなデメリットがあります。
- 就職できない職種ができる
- 就職、転職活動で履歴書に記載を求められ、不利益を被る可能性がある
- 解雇や退学処分となる可能性がある
- 離婚事由になる可能性がある
- 海外渡航を制限される場合がある
- インターネット上に罪を犯したという情報が残ることがある
- 再犯時に刑が重くなる可能性がある
罪を犯したことを十分反省したら、これらの不利益を被らないためにも、前科がつかないよう努める方がよいでしょう。
今回は前科によるデメリットを紹介するほか、よく誤解されているもののデメリットにはならないこと、前科をつけないための対処法をご紹介します。
前科がつくことでのデメリット
前科がつくとさまざまな場面でデメリットがあります。
就業・学業でのデメリット
まず、就業や転職、就学において以下のようなデメリットがあります。
一部の国家資格などが制限
前科がつくと、次に挙げる国家資格が必要な職業について、一定期間の資格制限を受けます。
| 職業 | 資格制限となる刑 | 制限内容 | 制限期間 | 法律 |
| 医師 | 罰金刑以上 | 業務停止や免許の取り消し | 3年以内 | 医師法 第7条2項 |
| 看護師、助産師、保健師 | 罰金刑以上 | 業務停止や免許の取り消し | 3年以内 | 保健師助産師看護師法 第14条2項 |
| 歯科医師 | 罰金刑以上 | 業務停止や免許の取り消し | 3年以内 | 歯科医師法 第7条2項 |
| 歯科衛生士 | 罰金刑以上 | 業務停止や免許の取り消し | 3年以内 | 歯科衛生士法 第4条1項 |
| 獣医師 | 罰金刑以上 | 業務停止や免許の取り消し | 獣医師法
第8条第2項3号 |
|
| 薬剤師 | 罰金刑以上 | 業務停止や免許の取り消し | 3年以内 | 薬剤師法 第8条 |
| 国家公務員 | 禁錮刑以上 |
|
刑執行終了まで | 国家公務員法 第5条3項2号、第8条1項1号、第38条1項、第43条、第76条 |
| 地方公務員 | 禁錮刑以上 |
|
刑執行終了まで | 地方公務員法 第9条の2 3項、8項、第16条1項、第28条4項 |
| 教員 | 禁錮刑以上 | 教員免許の失効 | 公立校の教員は刑執行終了まで。私立教員は役職などによる | 学校教育法 第9条1項 |
| 保育士 |
|
登録抹消 | 刑執行終了から2年 | 児童福祉法 第18条の5 第2項、3項 |
| 公認会計士 | 禁錮刑以上 |
|
刑執行終了、または執行猶予期間満了から3年 | 公認会計士法 第4条2項、3項、第21条1項 |
| 弁護士 | 禁錮刑以上 | 登録抹消 | 刑執行終了、または執行猶予期間満了から3年 | 弁護士法 第7条1項、第17条1項 |
| 司法書士 | 禁錮刑以上 | 登録抹消 | 刑執行終了、または執行猶予期間満了から3年 | 司法書士法 第5条1項、第15条4号 |
| 警備員 | 禁錮刑以上 | 就業不可 | 刑執行終了から5年 | 警備業法 第3条2項、第14条1項 |
また、刑事事件の刑罰は重い順に下記のものがあります。
- 死刑:絞首によって死に至らしめられる
- 懲役:刑務所に収容され、刑務作業に課せられる
- 禁錮:1ヵ月以上刑務所に収容される。刑務作業は課せられない
- 拘留:1日以上30日未満刑務所に収容される。刑務作業は課せられない
- 罰金:1万円以上の支払いを課せられる
- 科料:1,000円以上1万円未満の支払いを課せられる
表中の「禁錮刑以上」とは、禁錮・懲役・死刑のいずれか、「罰金刑以上」とは罰金・拘留・禁錮・懲役・死刑のいずれかを指します。
履歴書に記載する必要
履歴書には賞罰欄が設けられており、国家資格を要する職業に就きたい場合は前科の有無を必ず記載せねばなりません。
たとえ免許の取り消し期間や業務停止期間が満了していても、前科があるために不利になる可能性は高いでしょう。
一方、一般企業では、必ずしも履歴書に記載しなくてもかまいませんし、面接などの場でわざわざ申告する必要もありません。
しかし、前科があるかどうか質問された場合は、正直に答える必要があります。
もし、うそをついて、後から虚偽が発覚すれば、経歴を詐称したとして解雇される可能性もあるでしょう。
解雇・退学処分の可能性
勤務先の就業規則に、解雇事由として「有罪判決を受けたとき」などと記載されていれば、解雇となる可能性があります。
ただし、就業規則に記載がなくても、業務に著しく影響を与えたり、会社の信用に影響したりした場合は解雇事由となり得るでしょう。
学生の場合は学則に準じます。学校が懲戒処分事由として、「犯罪行為があったとき」や「有罪判決を受けたとき」などと定めていれば退学となる可能性もあるでしょう。
婚姻における不利益
有罪判決を受けると、法定離婚事由に該当するとみなされる可能性があります。
法定離婚事由とは、民法第770条1項で次のように定められており、配偶者から離婚を求められれば応じざるをえない離婚理由のことです。
(裁判上の離婚)
第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
引用元:民法|e-Gov 法令検索
前科がつくと、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するとされる可能性があります。
パスポート・海外渡航での制限
前科があると、パスポートの発給や海外渡航に制限がある場合があります。
入国審査が厳しい国へは渡航できない可能性もあるでしょう。
また、入国が認められない国へのビザは発給されませんし、刑事裁判中や執行猶予期間中の出国は認められていないため、パスポートの発給も受けられません。
インターネット上におけるデメリット
刑事事件となり、逮捕、起訴されれば、何らかの形で報道される可能性が高いでしょう。
時間が経てば人々の記憶からは消えますが、インターネット上のニュース記事やSNSの投稿は、削除申請でもしない限り、長期にわたって残る可能性があります。
そのため、知られたくない人に知られる可能性は消えないでしょう。
再犯時におけるデメリット
警察や検察は逮捕歴や犯罪歴を記録しており、再犯かどうかもすぐに確認できます。
再犯は初犯よりも重い刑罰を受ける可能性が高く、逮捕や起訴をされれば非常に不利です。
また、最初の犯罪による刑の執行から5年以内に、新たに罪を犯せば、累犯とされ、さらに重い刑を科せられる可能性があります。
(再犯加重)
第57条 再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。
引用元:刑法|e-Gov 法令検索
前科があってもデメリットとならない事項
以下で紹介する事項は、よく前科によって被る不利益だと誤解されていますが、実際には関係しません。
戸籍や住民票などに記載されることはない
前科の有無は戸籍や住民票に記載されません。
前科についての情報は非常に秘匿性の高いものです。
他人の目に触れる可能性があるところには掲載されません。
選挙権は失効しない
選挙権は、刑の執行中は失いますが、刑期を終えれば再び得られます。
前科があることを理由には失効しません。
選挙権を失うのは公職選挙法第11条などに定められる次に該当する方です。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の場合を除く)
- 公職にある間に刑に処せられ、その執行を終わるか免除を受けた者で、実刑期間経過から5年以内の者。または執行猶予中の者
- 公職選挙法等で定める選挙に関する罪を犯したために、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法が定める罪を犯したために、選挙権、被選挙権が停止されている者
国からの受給権利は失わない
前科があっても、年金や生活保護など、国からの手当てについての受給権利は失いません。
年金法にも生活保護法にも、前科がある方への支給を制限するような定めはないからです。
ローンやクレジット審査でのデメリットはない
ローンやクレジットの審査は、信用情報機関の情報を元におこなわれます。
信用情報に前科の有無が記載はないため、前科があることだけを理由に借り入れが制限されることはありません。
「前科がつく」とは、どういうこと?
「前科がつく」とは、刑事裁判で有罪判決を受け、それが確定したことをいいます。
刑務所で服役するかどうかは関係なく、執行猶予がついたとしても判決内容が有罪であれば前科となるものです。
前科についての理解を深めておきましょう。
前科・前歴との違い
前科と似た言葉に「前歴」があります。
混同されやすい言葉ですが、両者は対象となる状況が異なります。
「前科」と「前歴」の違いは下記のとおりです。
| 対象となる状況 | |
| 前科 | 刑事裁判で有罪判決が確定した(執行猶予となった場合も含む)。 |
| 前歴 |
|
交通違反では前科はつかない?
交通違反の場合、行政処分となれば前科はつきません。
交通違反の点数制度上5点以下の違反であれば、刑事処分ではなく行政処分となり、その点数に応じて免許停止や免許取消、免許保留などの処分が課される程度で済みます。
ただし、反則金の支払いを拒んだり、出頭通知に従わなかったりした場合は、刑事処分となり前科がつく可能性もあるでしょう。
前科をつけないためには
前科がつくと、さまざまな不利益が生じます。
罪を犯してしまったことを十分に反省したら、できる限り前科が付かないよう努める方がよいでしょう。
そのためには、以下のことを心掛けましょう。
不起訴を獲得する
前科をつけないためには、不起訴処分を獲得することが大切です。
というのも、日本の刑事裁判では起訴後の有罪率は99%以上と非常に高いからです。
裁判所が発表している令和2年度の司法統計によると、起訴事件65,560件のうち無罪判決が出たのはわずか71件でした。
起訴されれば、まず有罪判決が下され、前科がついてしまうと考えてよいでしょう。
そのため、起訴されないことが非常に重要なのです。
【参考記事】令和2年度司法統計|第9表 刑事訴訟事件の種類及び終局区分別既済人員―地方裁判所
早めの示談交渉
不起訴処分を獲得するには、被害者がいる事件であれば示談を成立させることが大切です。
示談が成立したということは、本人も深く反省し、被害者の処罰感情が和らいだとみなされやすいためです。
不起訴になる可能性は低くありません。
警察が発表している令和4年度の犯罪白書によると、令和3年に検挙された刑法犯169,606人のうち、起訴となったのは62,296人と起訴率は約37%に止まります。
事件の内容にもよりますが、示談によって不起訴となる可能性は十分にあると考えてよいでしょう。
ただし、示談交渉はすぐに成立するものではありません。
ある程度の時間を要するため、可能な限り早めに始める方がよいでしょう。
【参考記事】令和4年版 犯罪白書
深く反省し、早めに弁護士に依頼する
前科をつけないためには、起訴されないことが大切です。
そのためには、深く反省し、できるだけ早い段階で被害者との示談を成立させることが肝要といえます。
しかし、逮捕されてから起訴に至るまでの時間は約3週間しかありません。
自身が勾留されている場合はもちろん、勾留されなかった場合でも早急に弁護士に依頼し、示談成立に向けて動いてもらった方がよいでしょう。
被害者が簡単に許してくれることはほとんどなく、交渉には時間と交渉力が必要になるからです。
弁護士へは、逮捕されそうな段階や逮捕直後など、可能な限り早い段階で依頼するのが望ましいでしょう。
さいごに:早めに弁護士に依頼する
有罪判決を受けて前科がつくと、社会的に大きな不利益を受けてしまいます。
罪を犯してしまったことを十分反省したら、できるだけハンデのない状態でもう一度やり直すためにも、前科がつくのは避けたいところです。
そのためにも、できるだけ早い段階で弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、被害者と示談交渉をしてもらえたり、裁判官に意見してもらえたりするなど、力を尽くしてもらえるでしょう。
その結果、不起訴処分を獲得し、前科がつくのを逃れられる可能性が高まります。
事件を起こしてしまい、逮捕されたらできるだけ早めに弁護士に依頼しましょう。